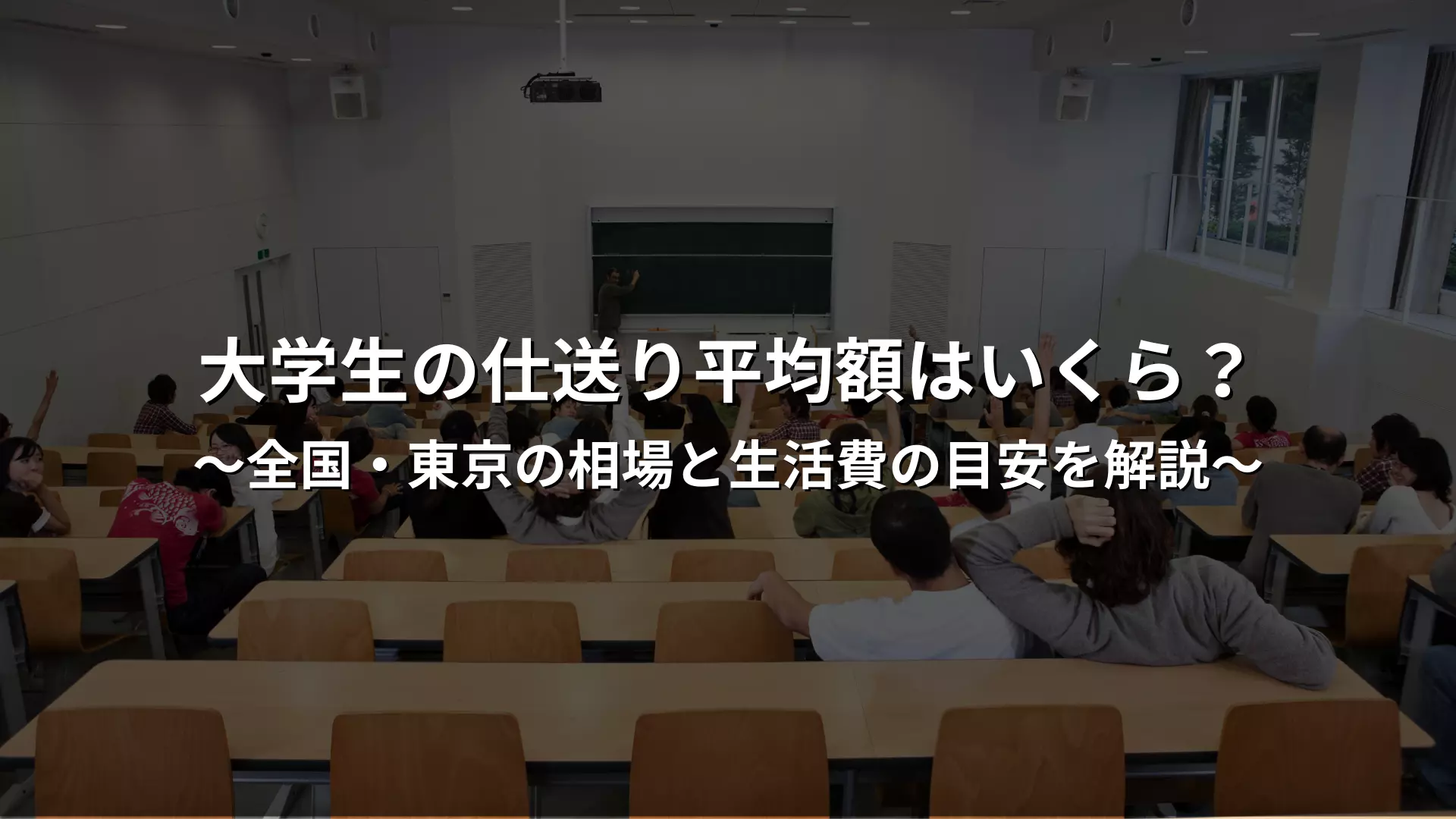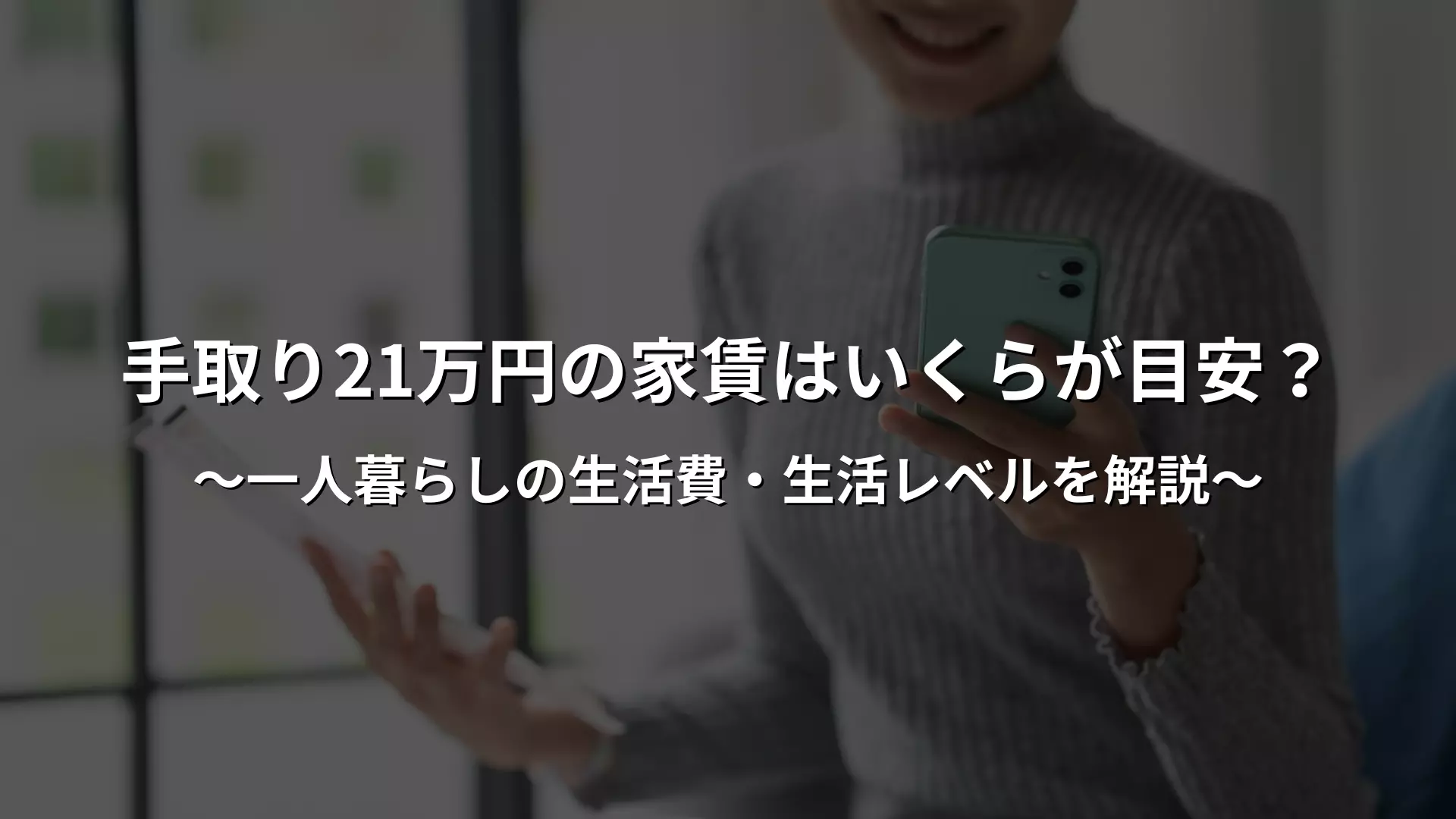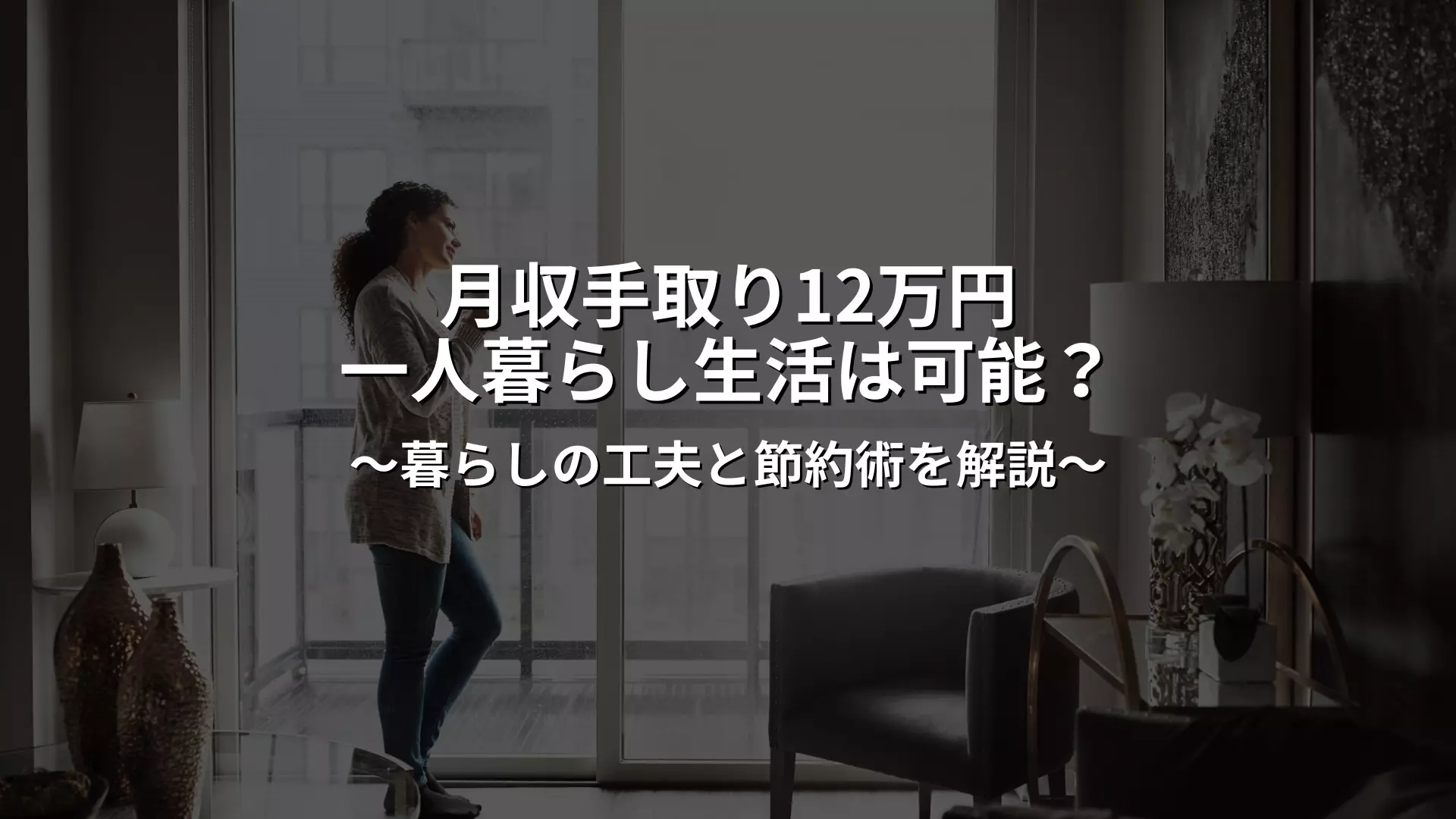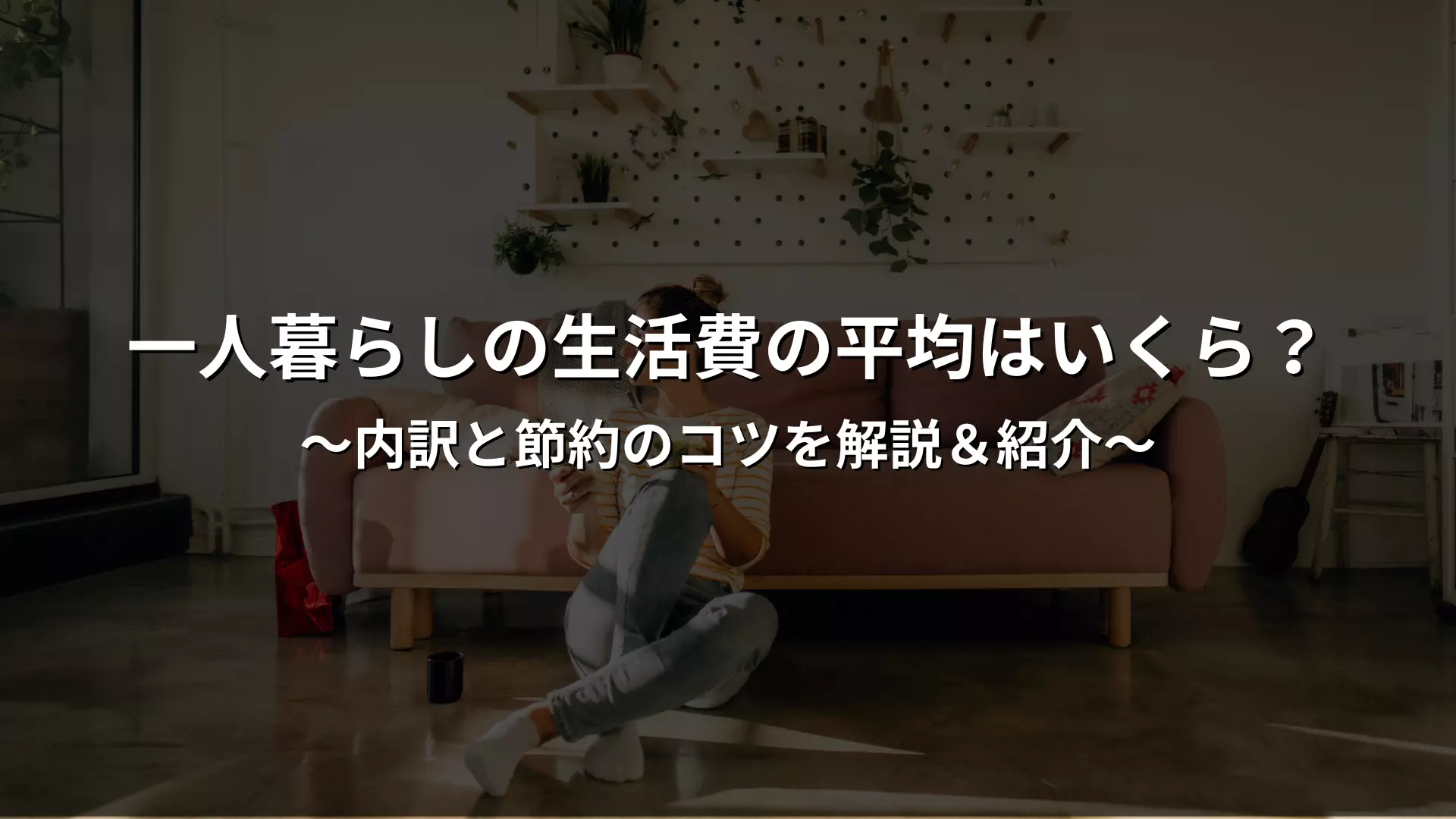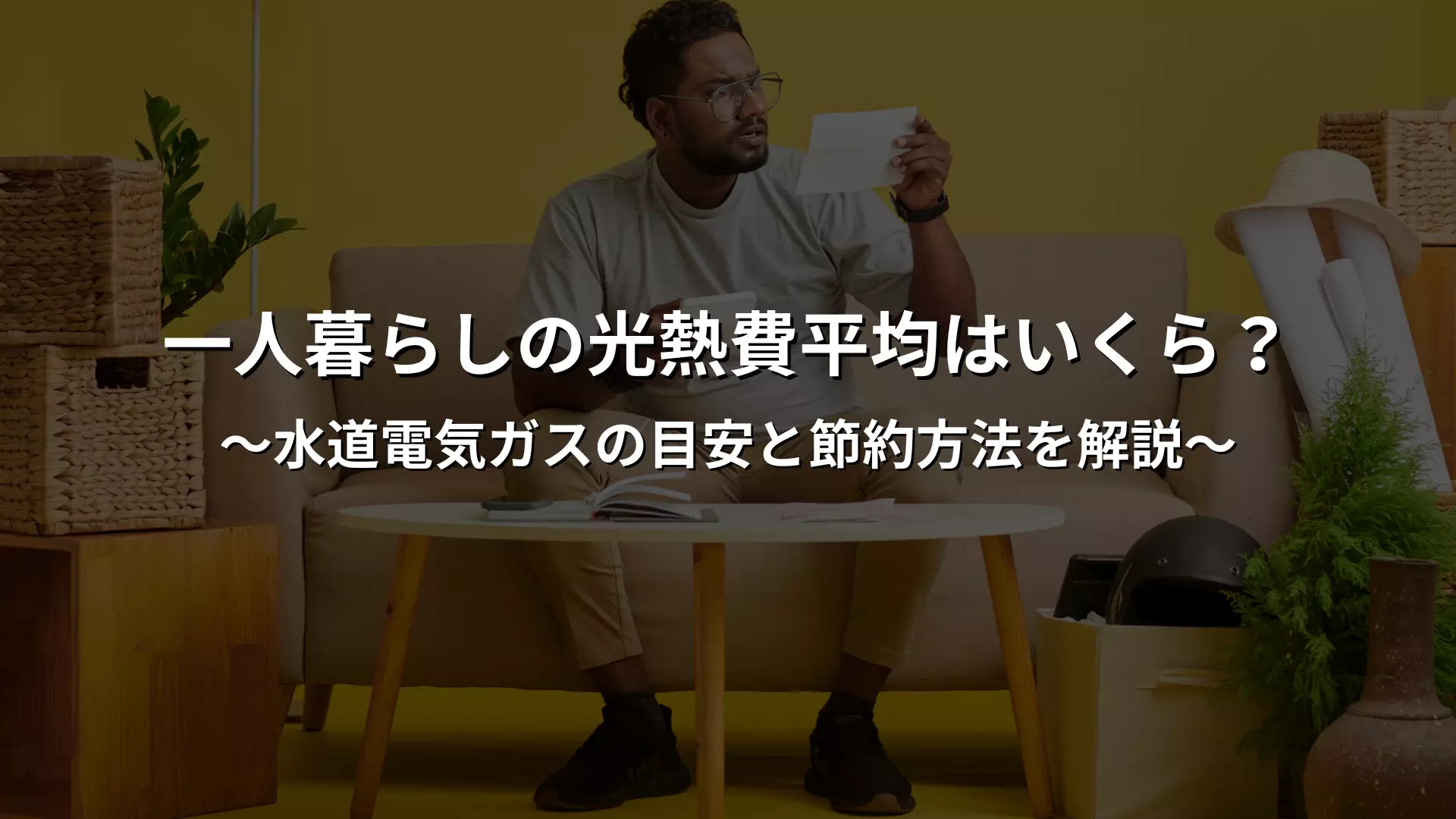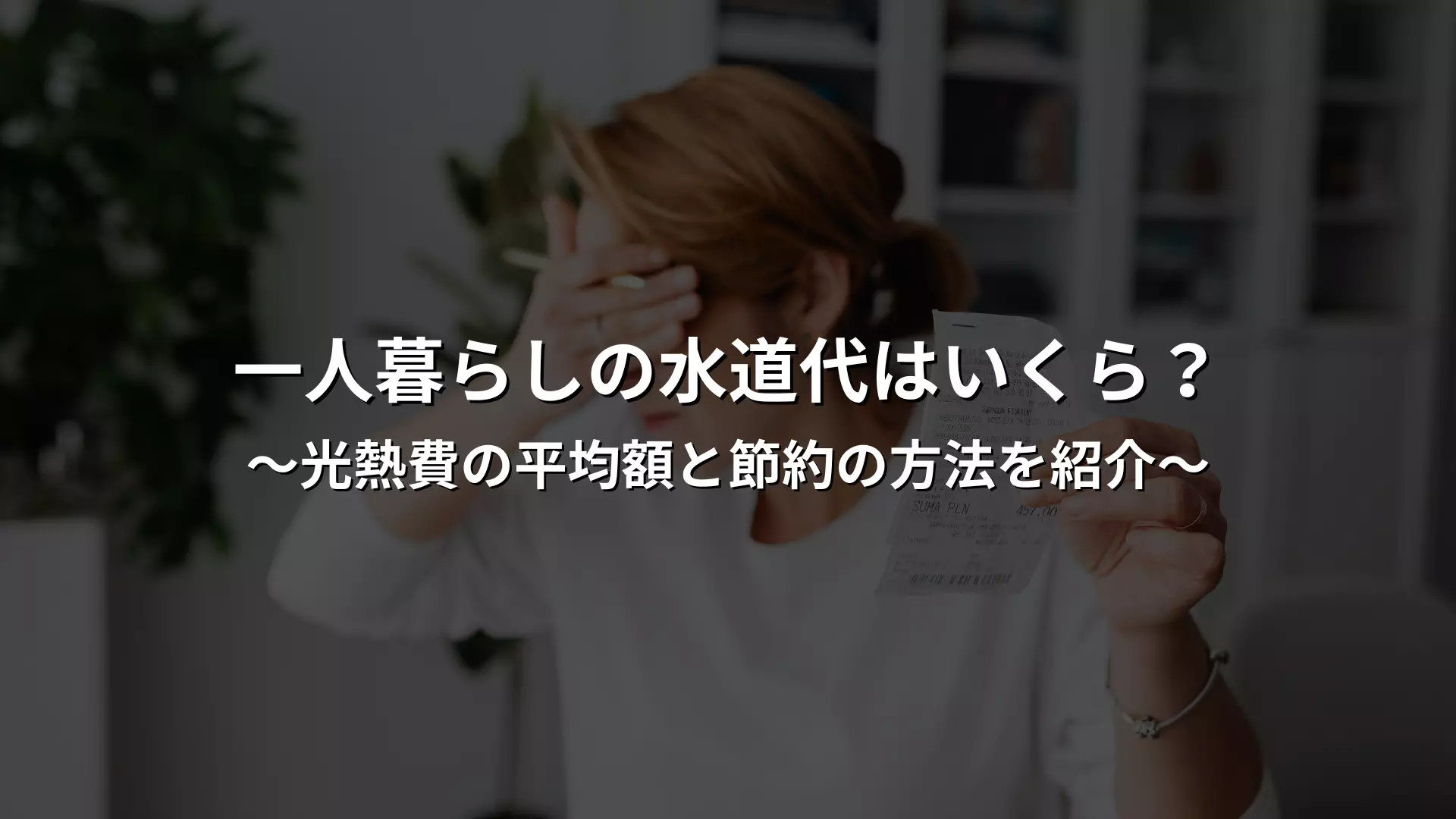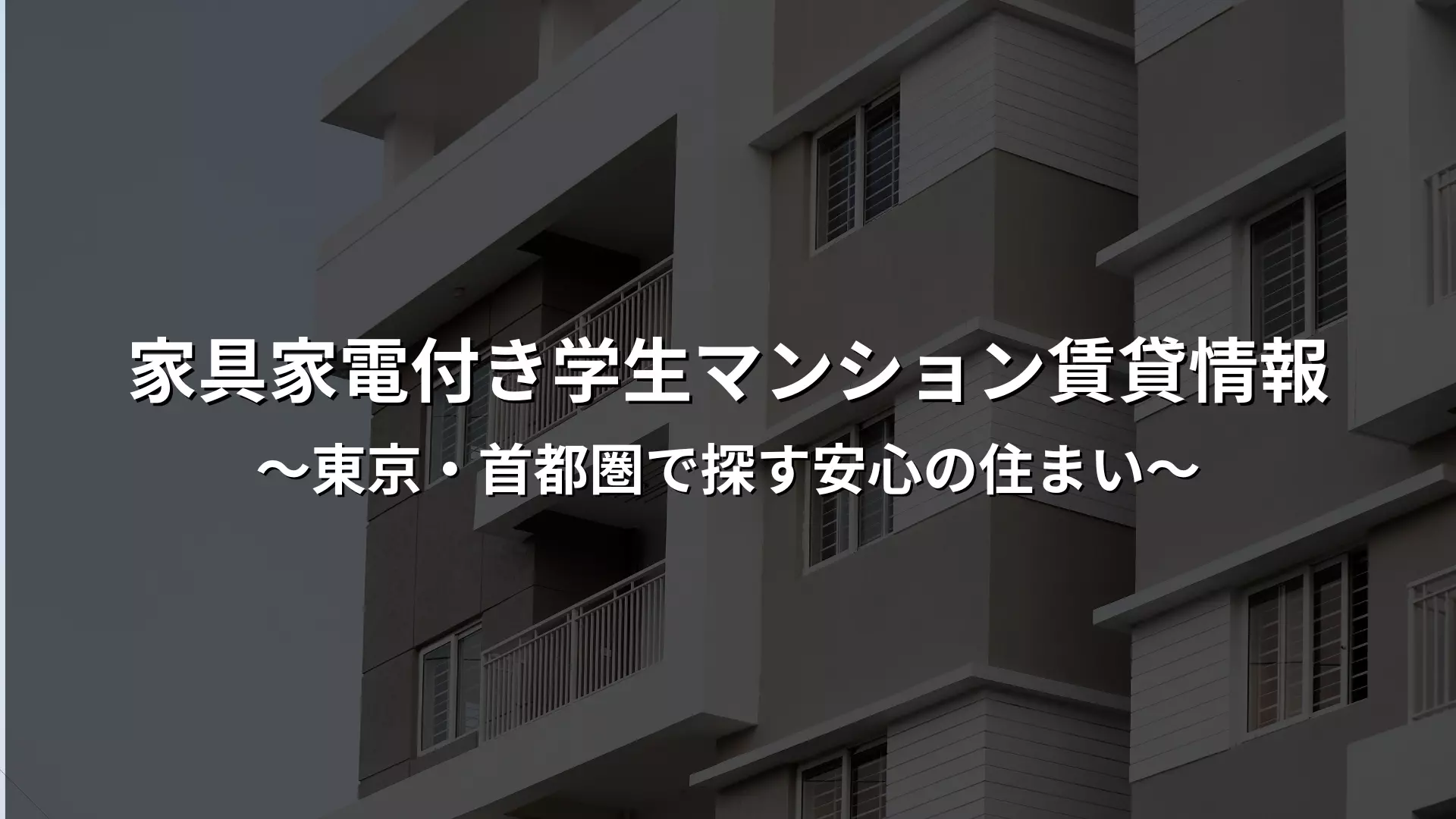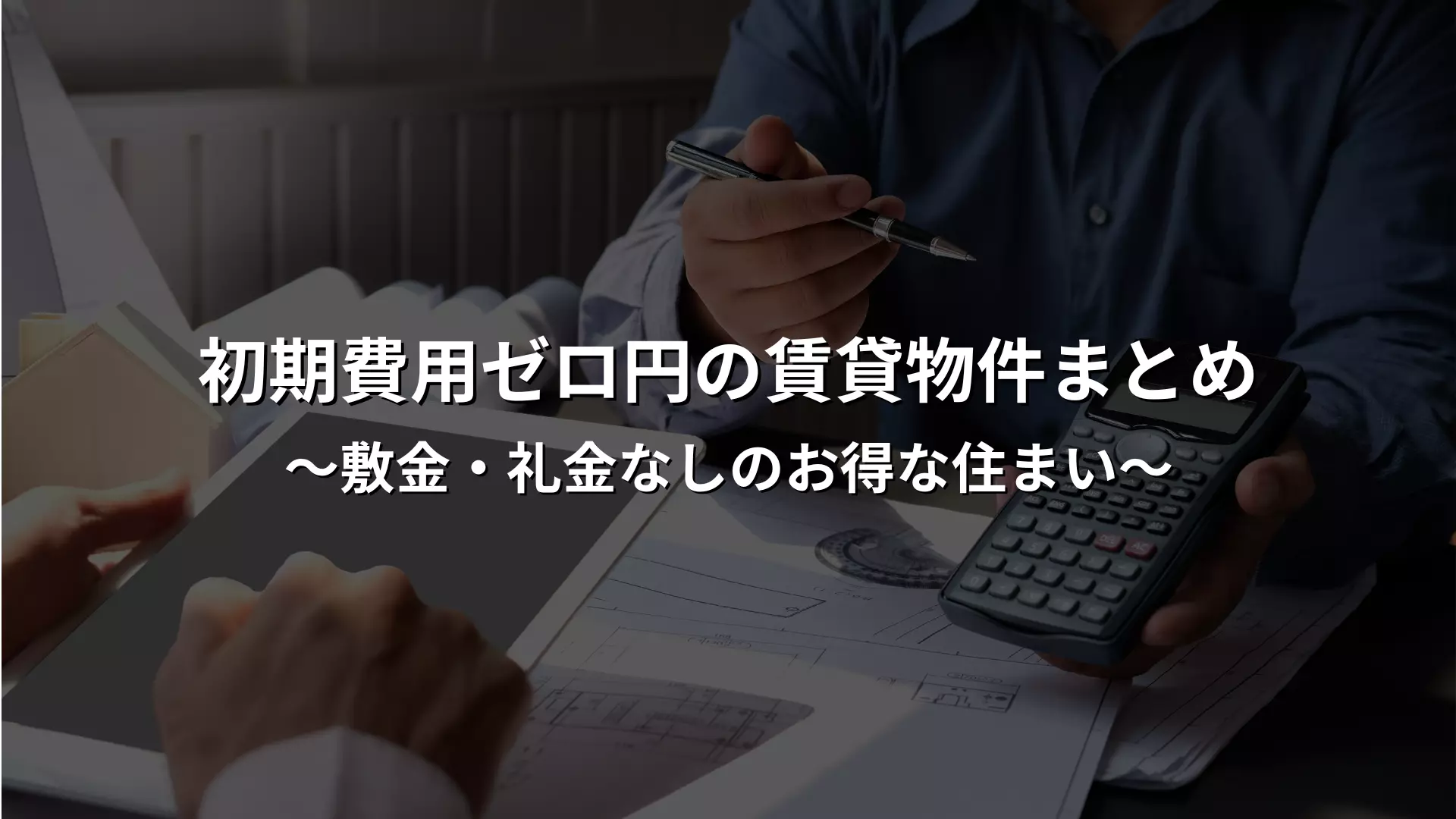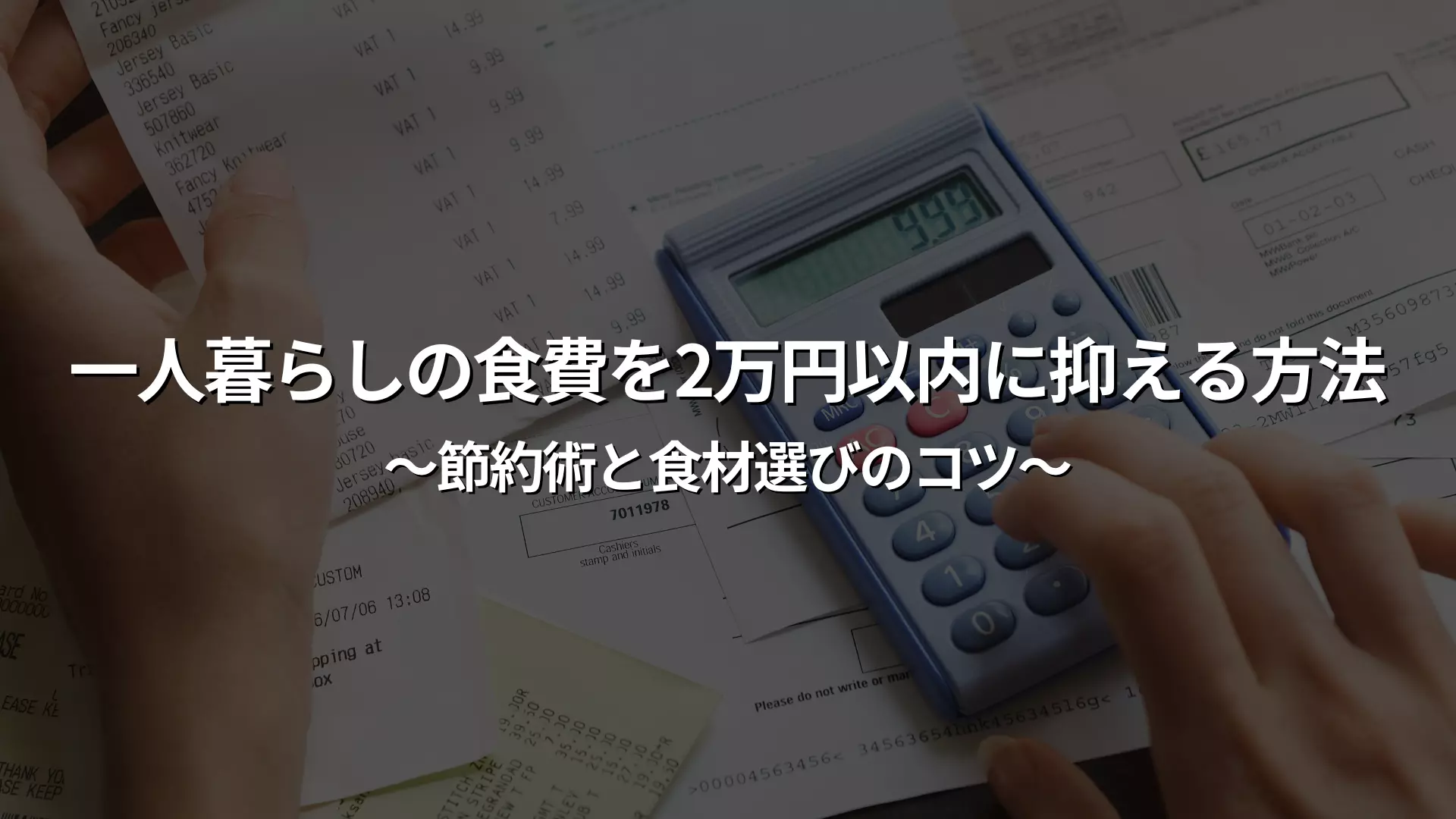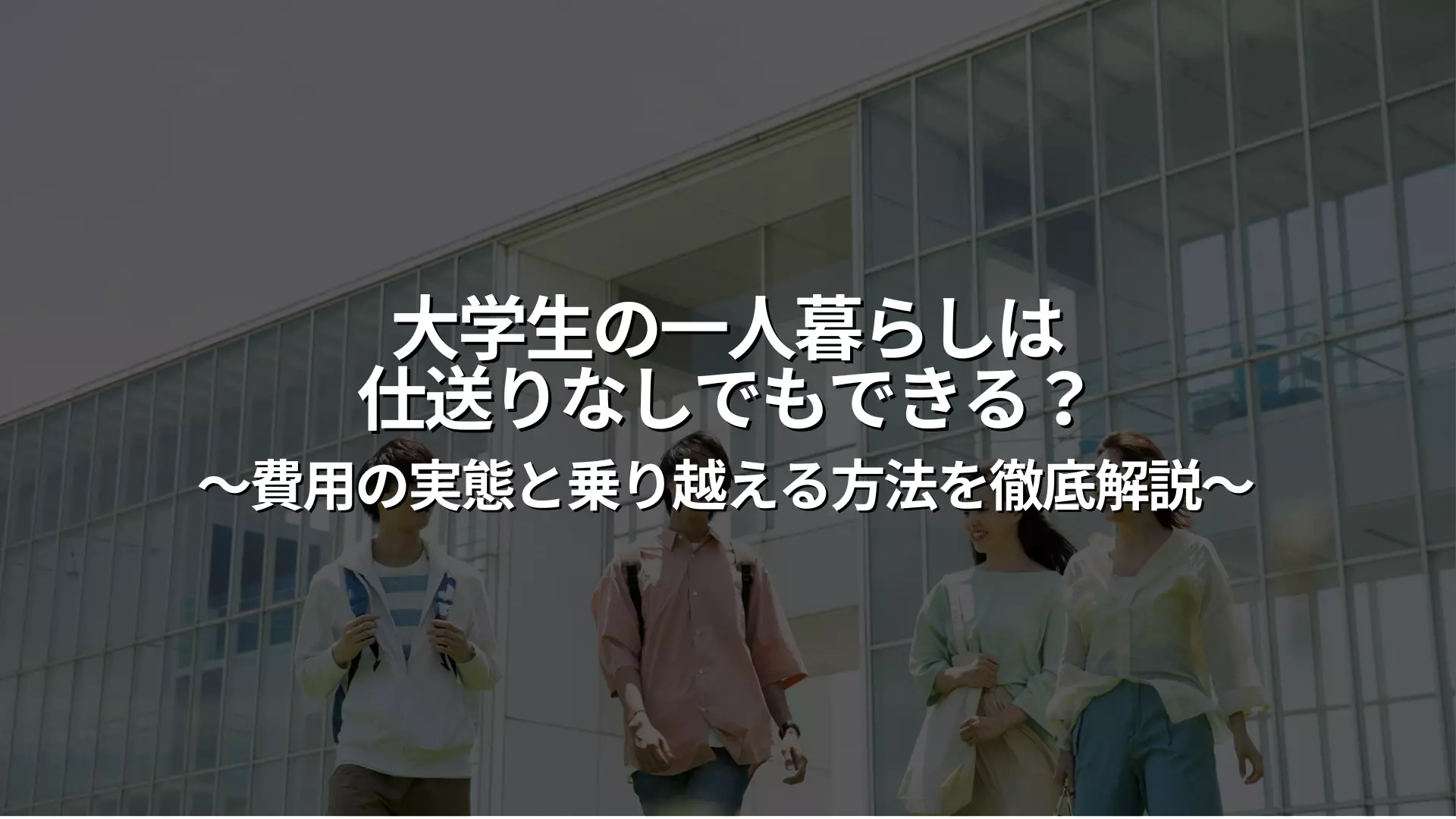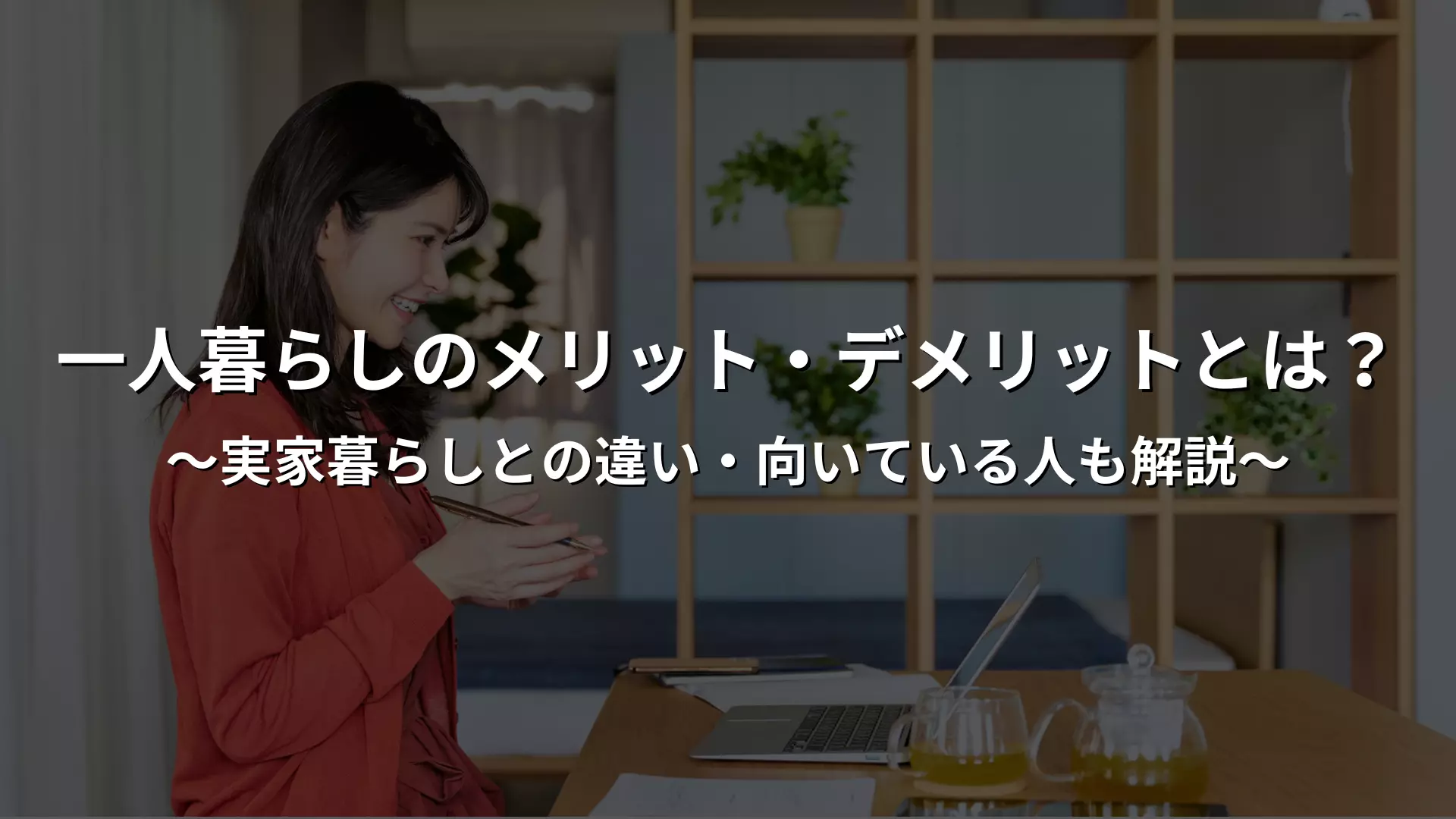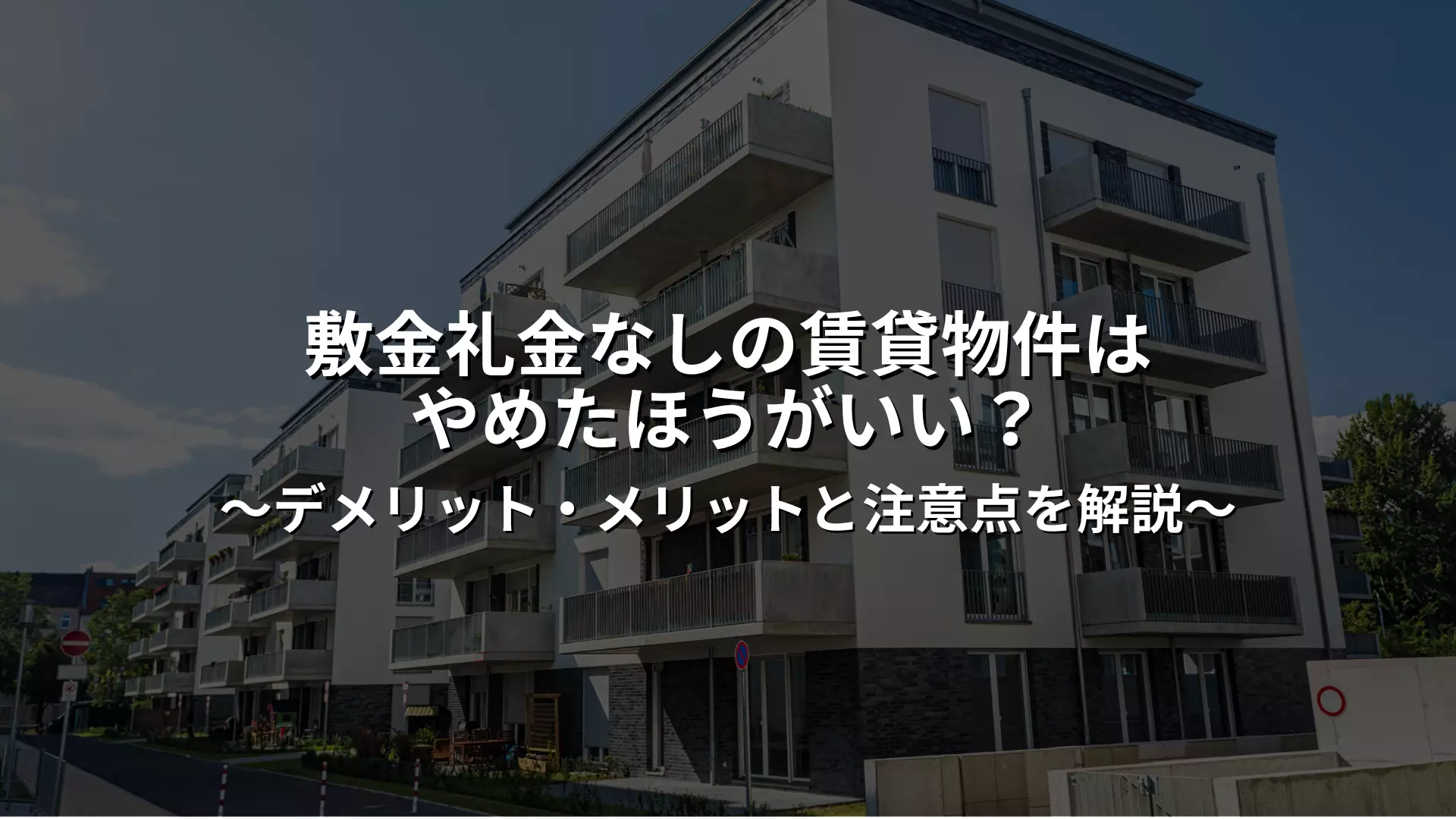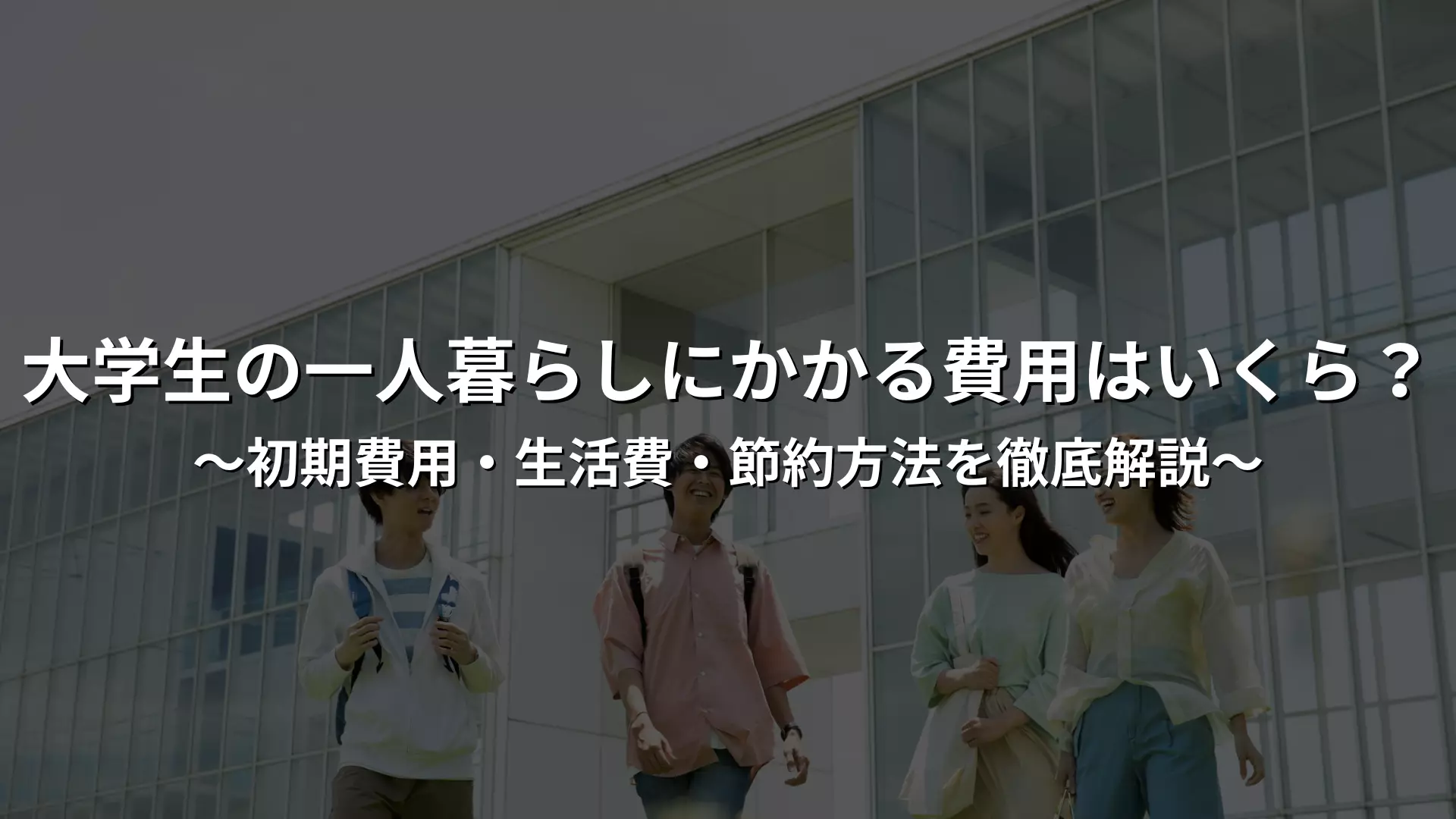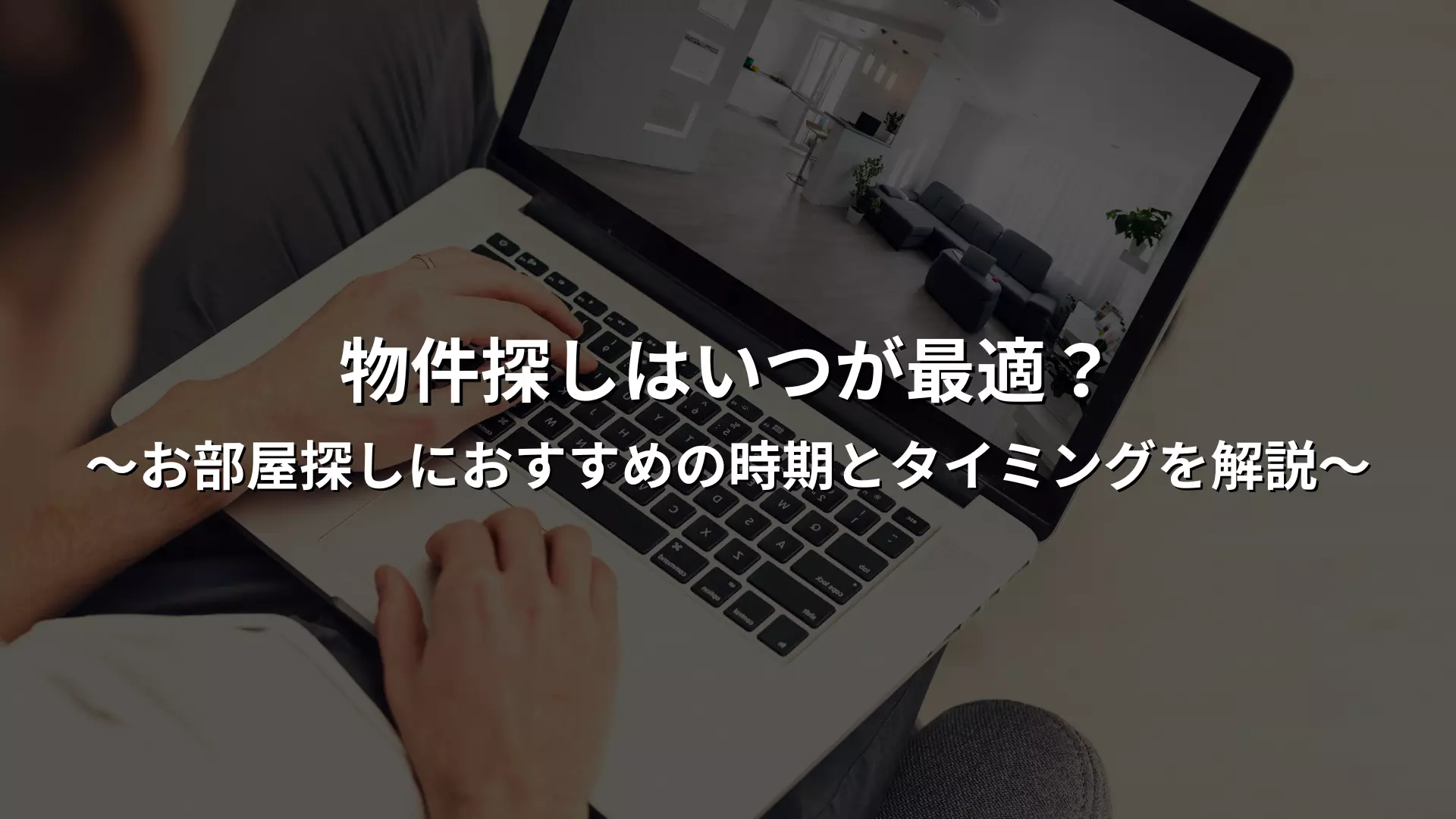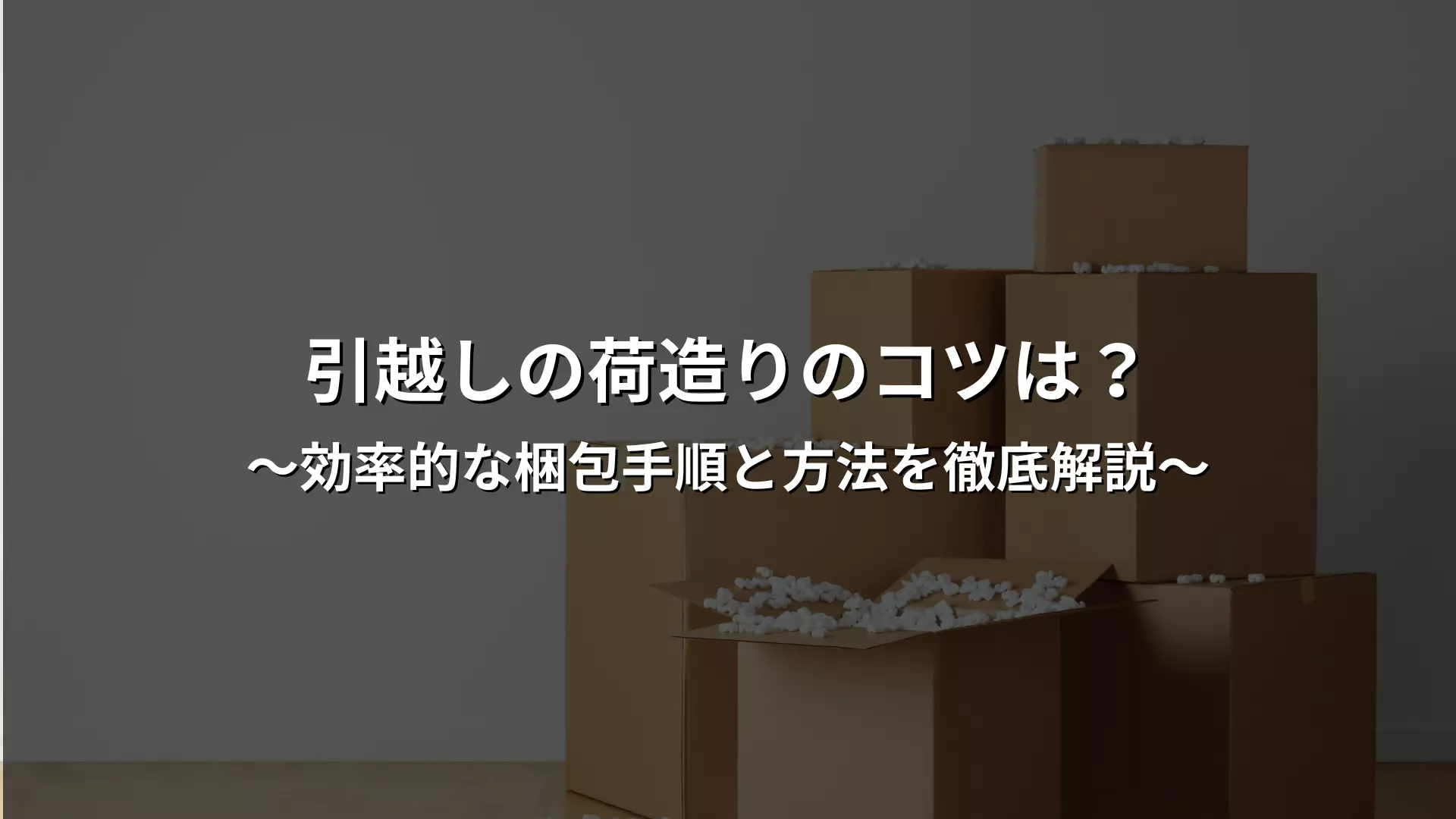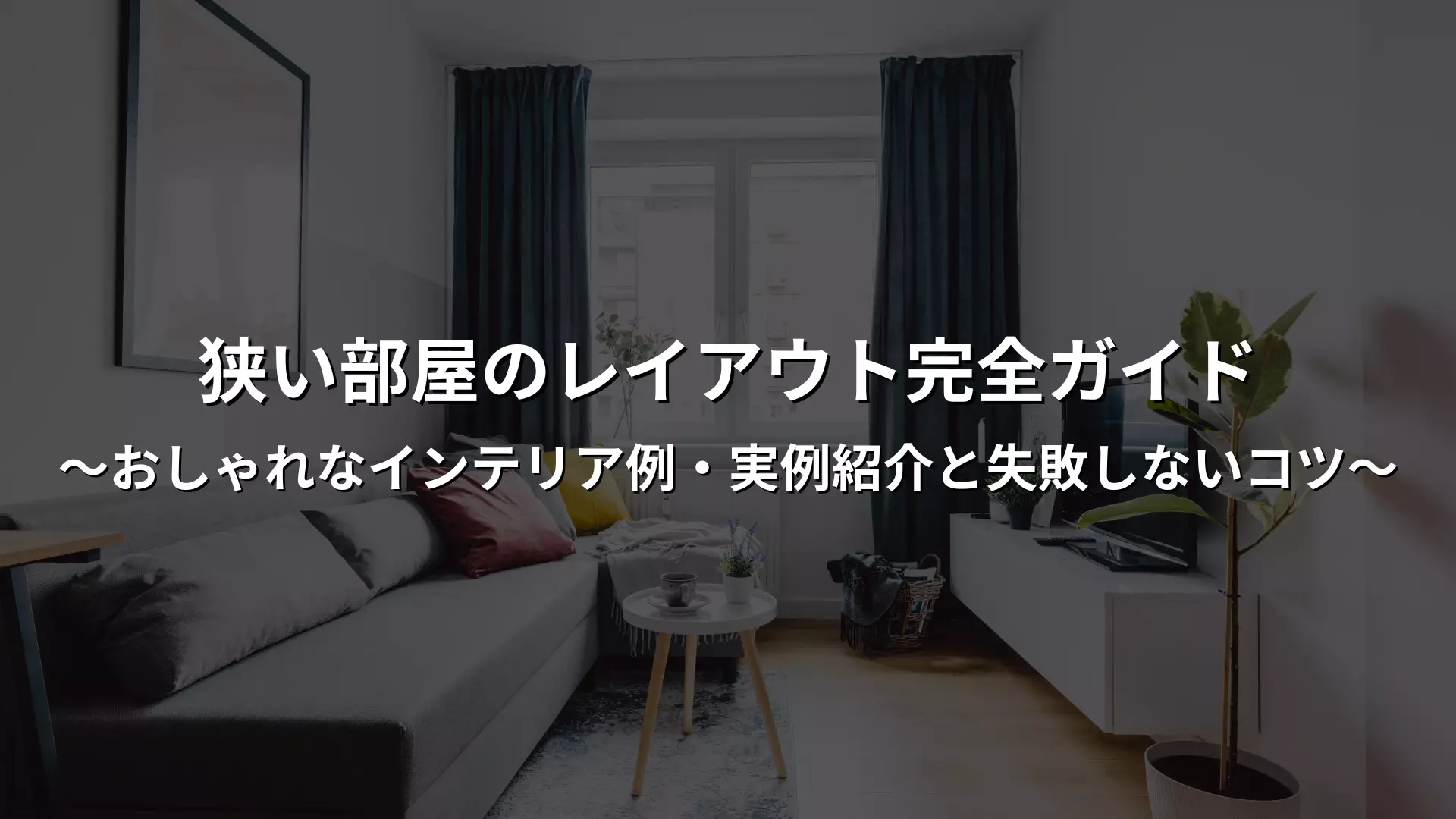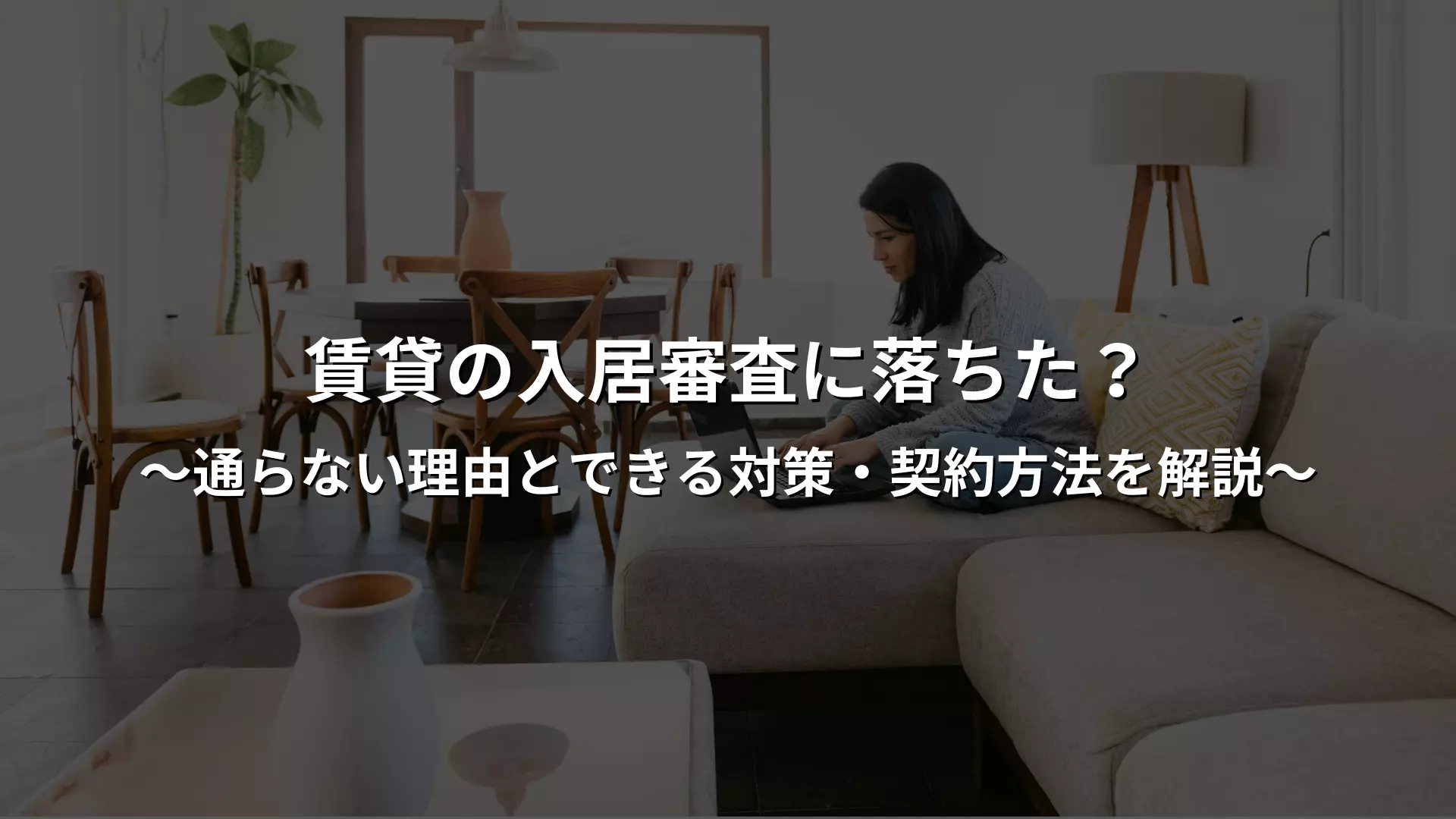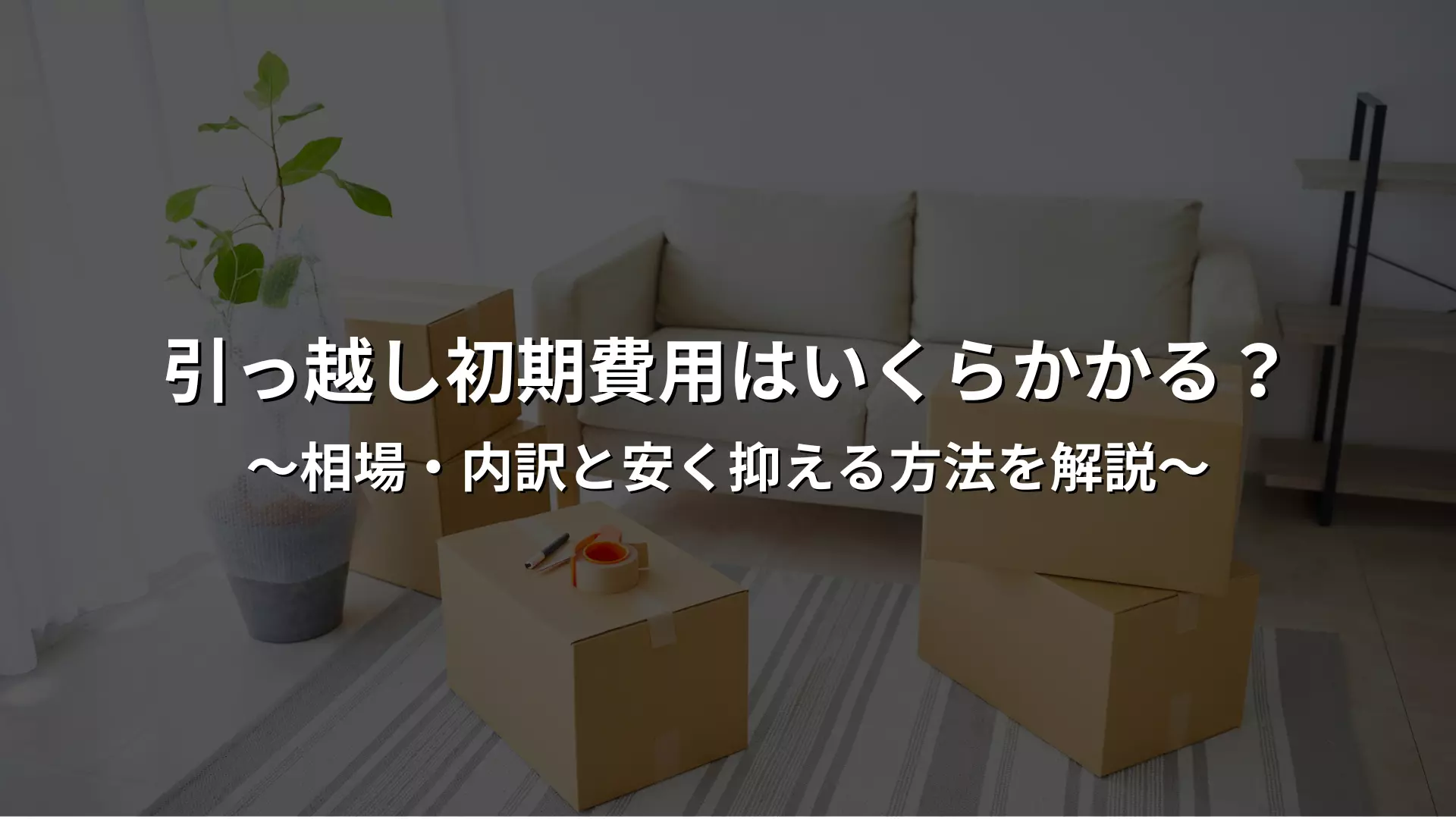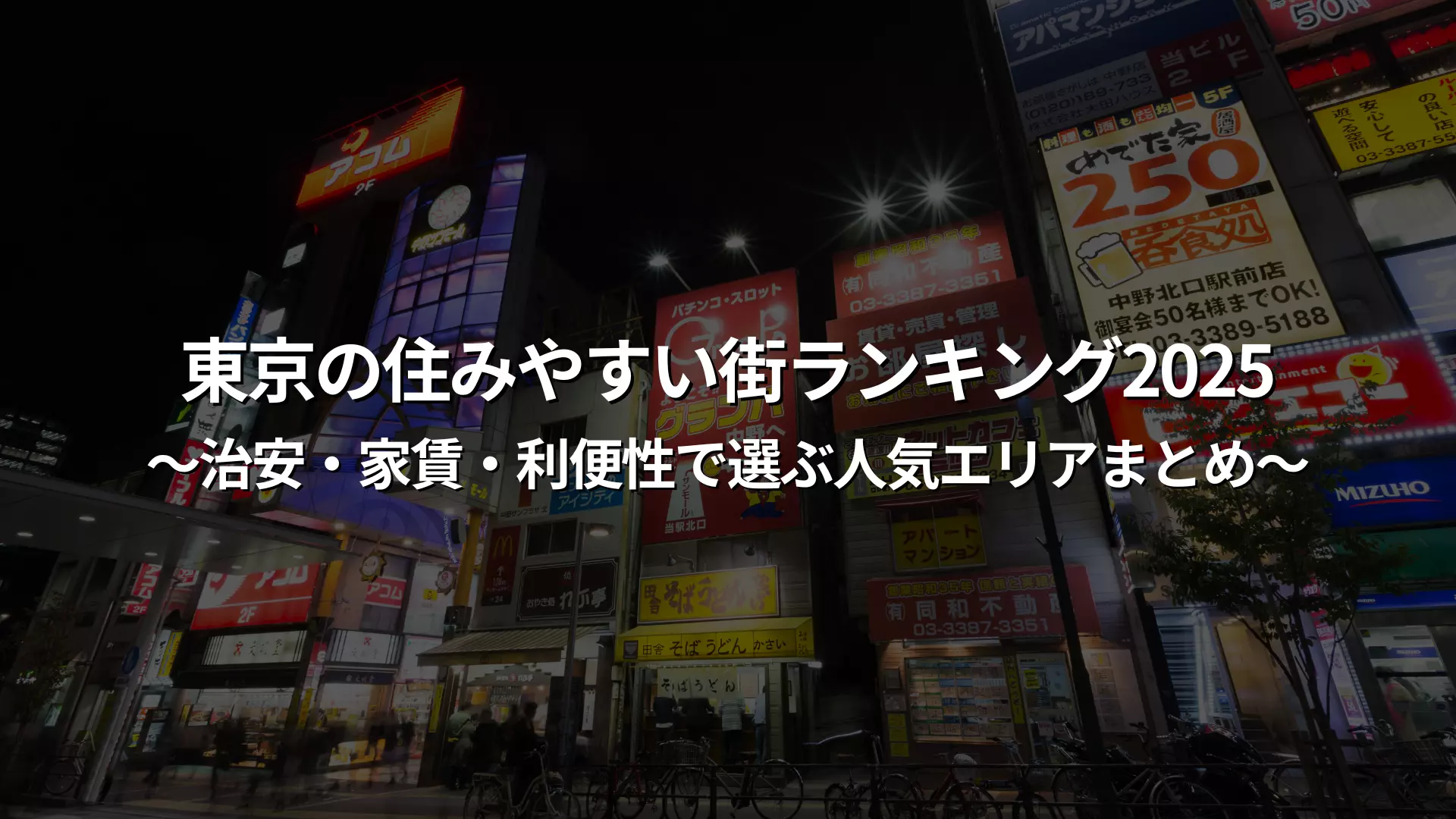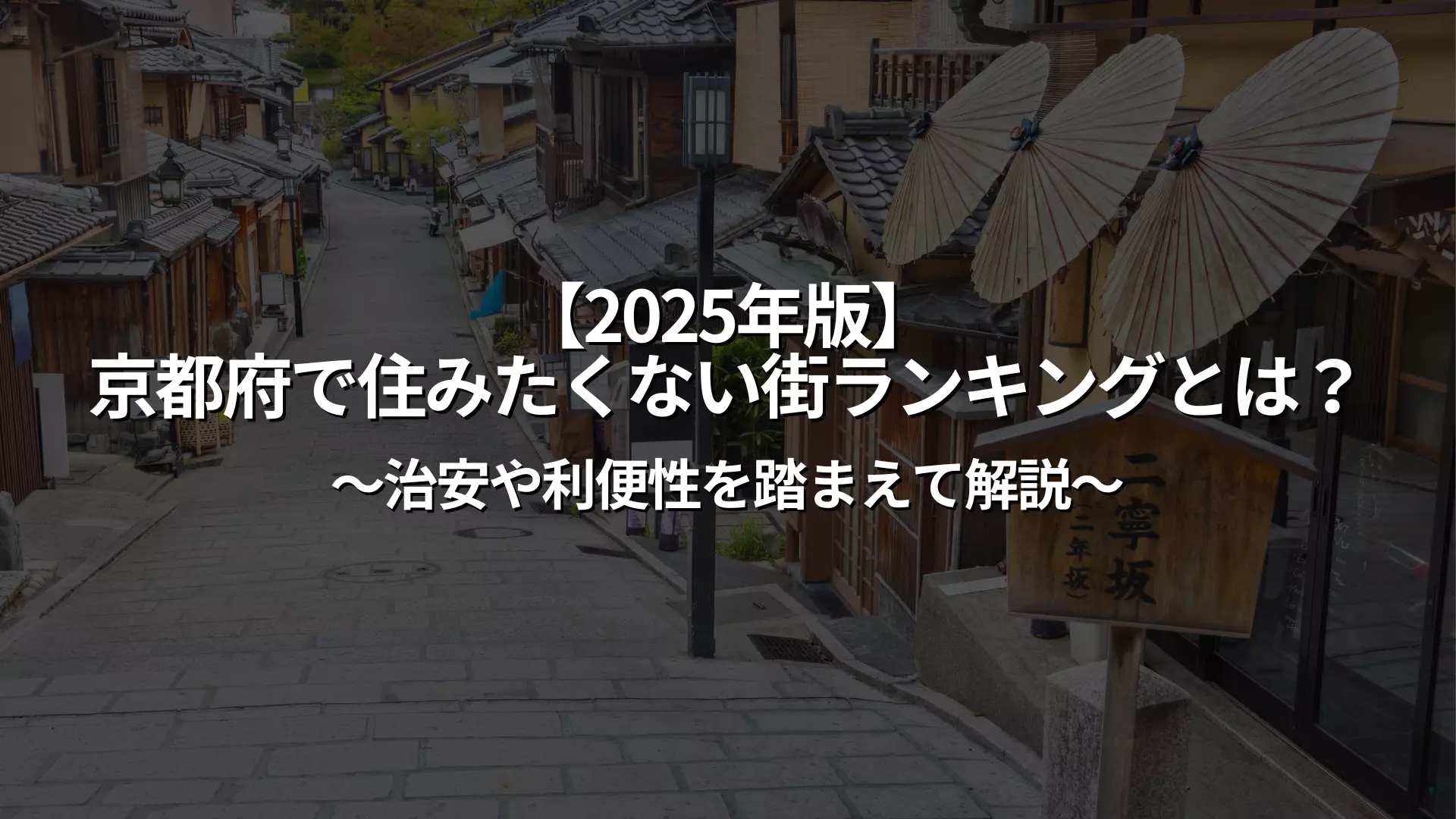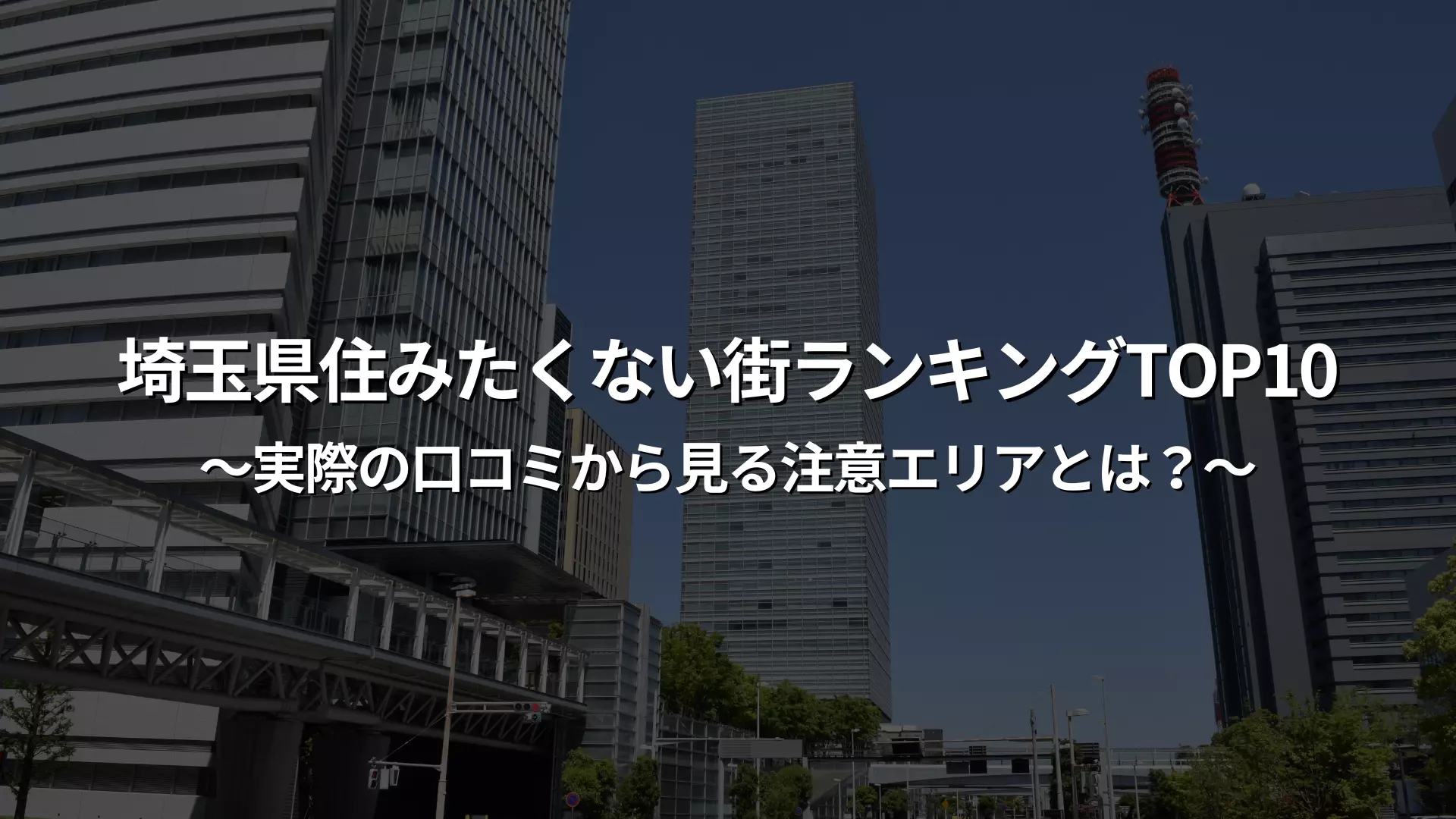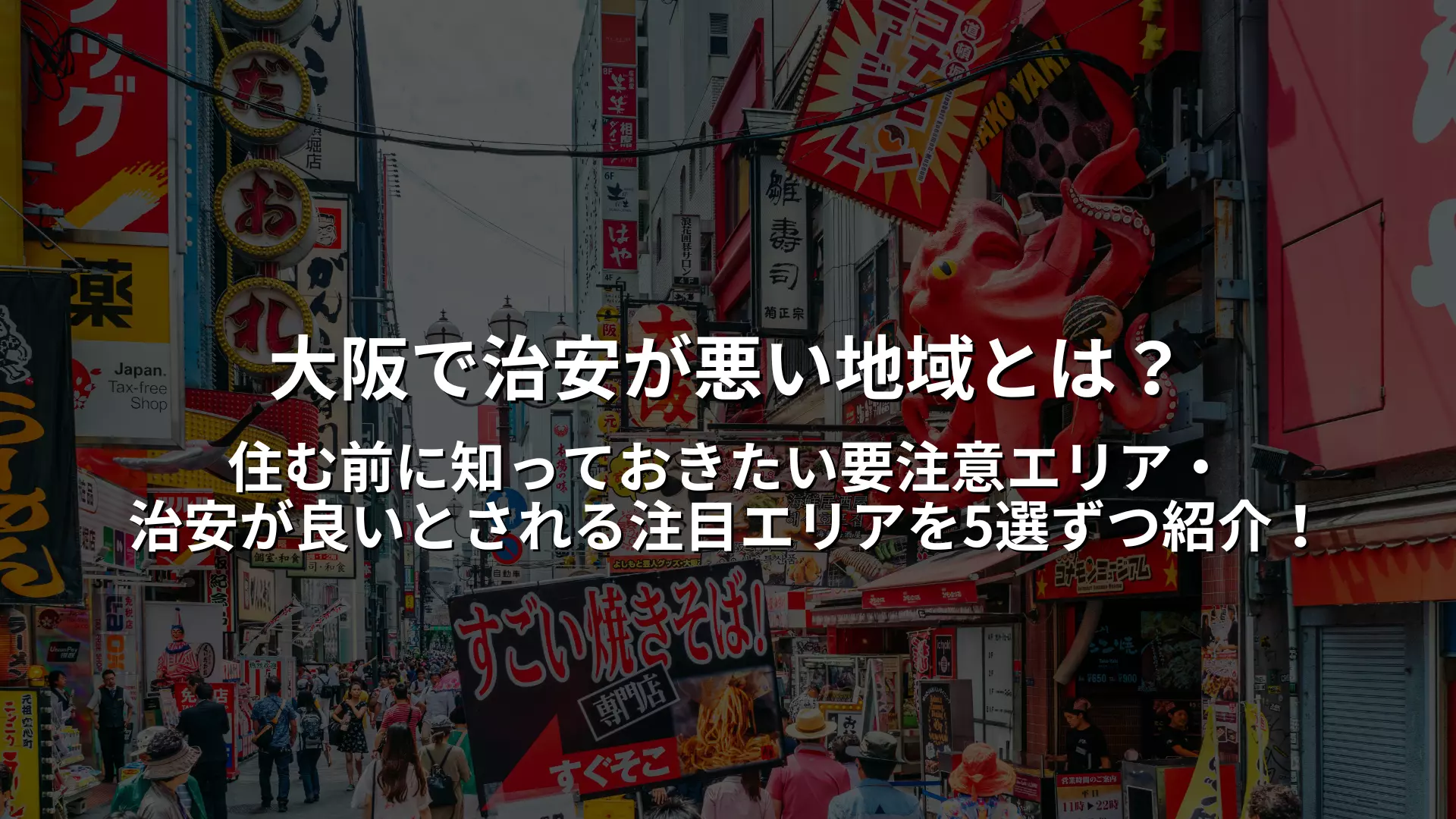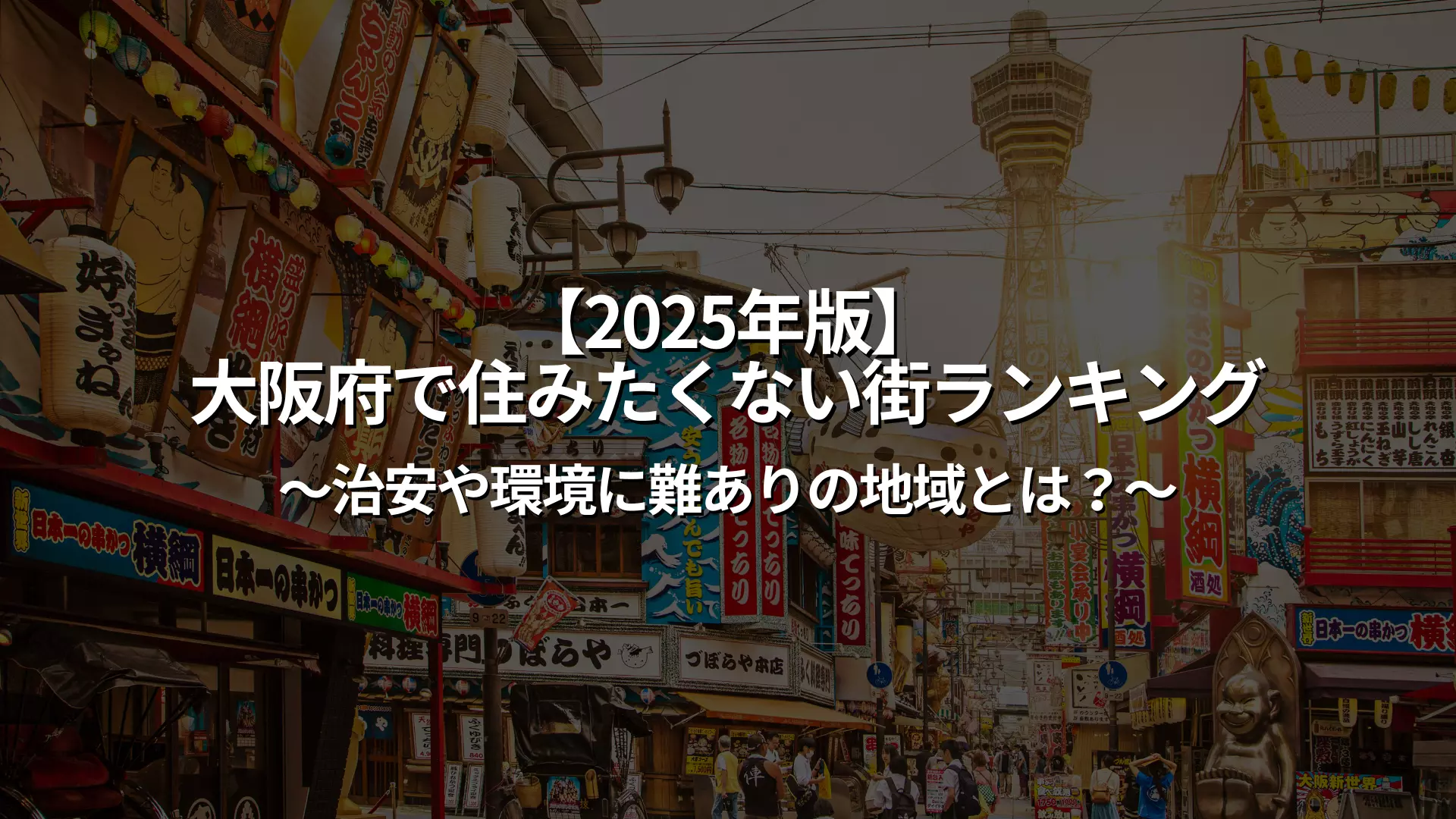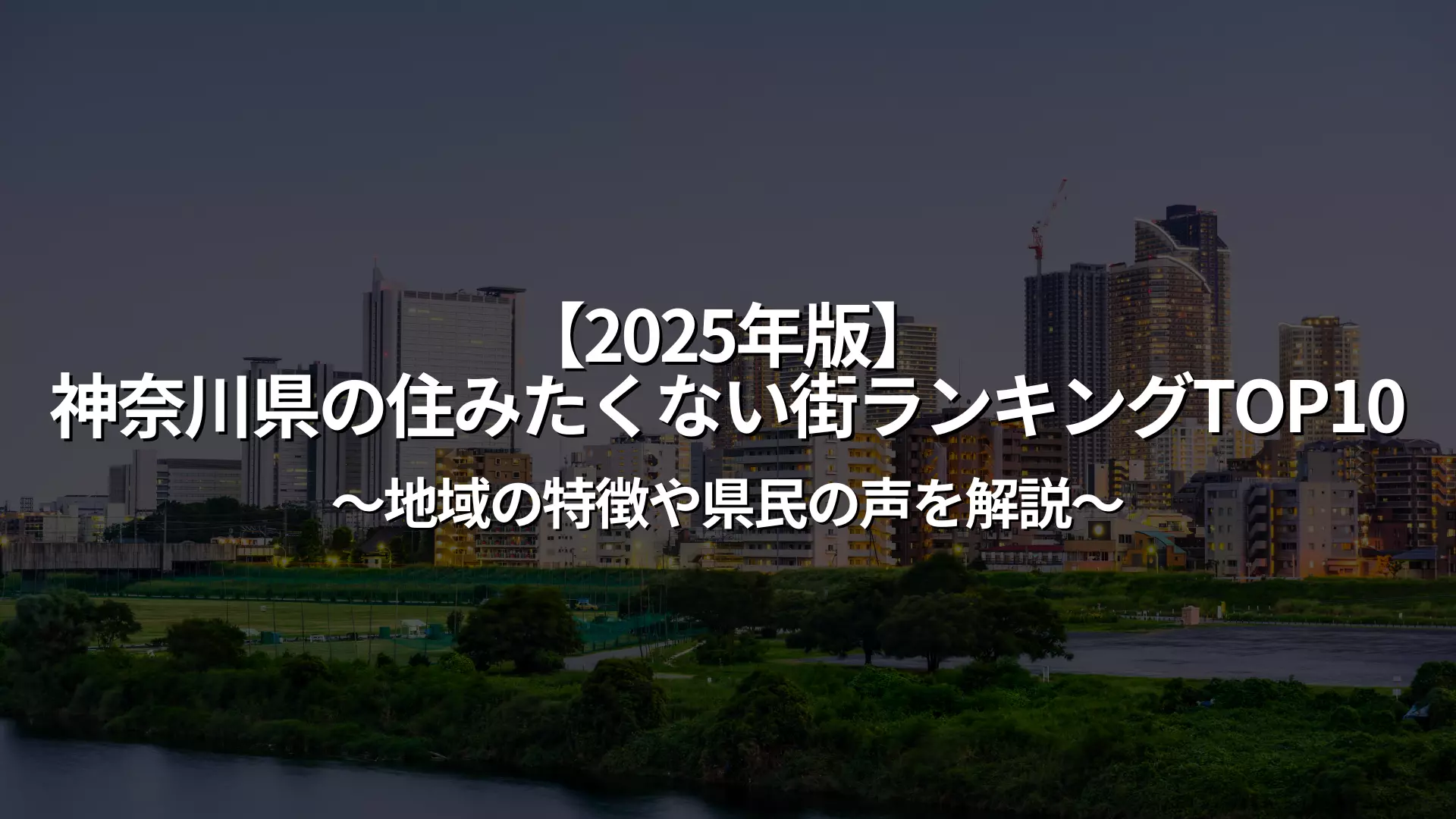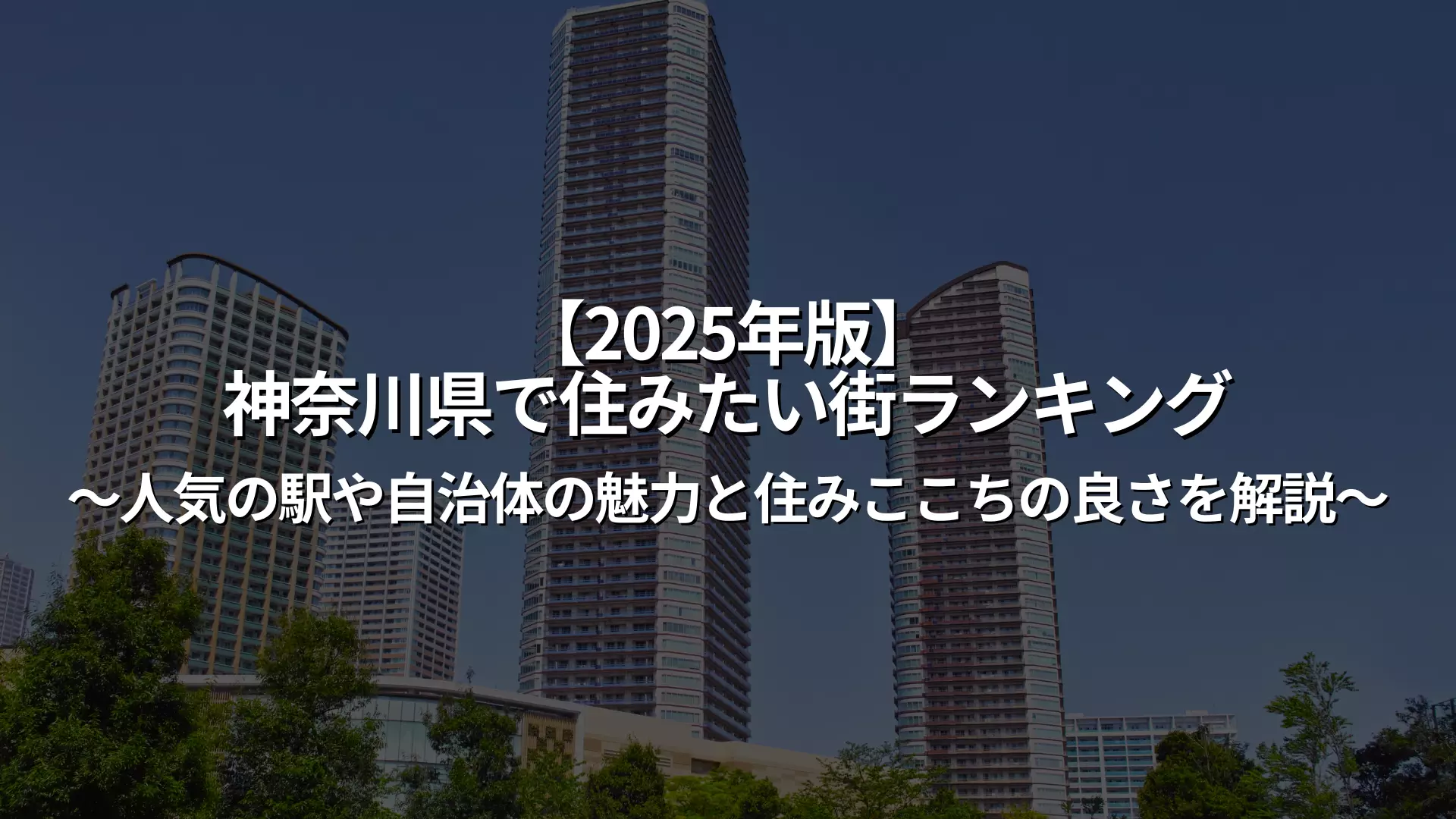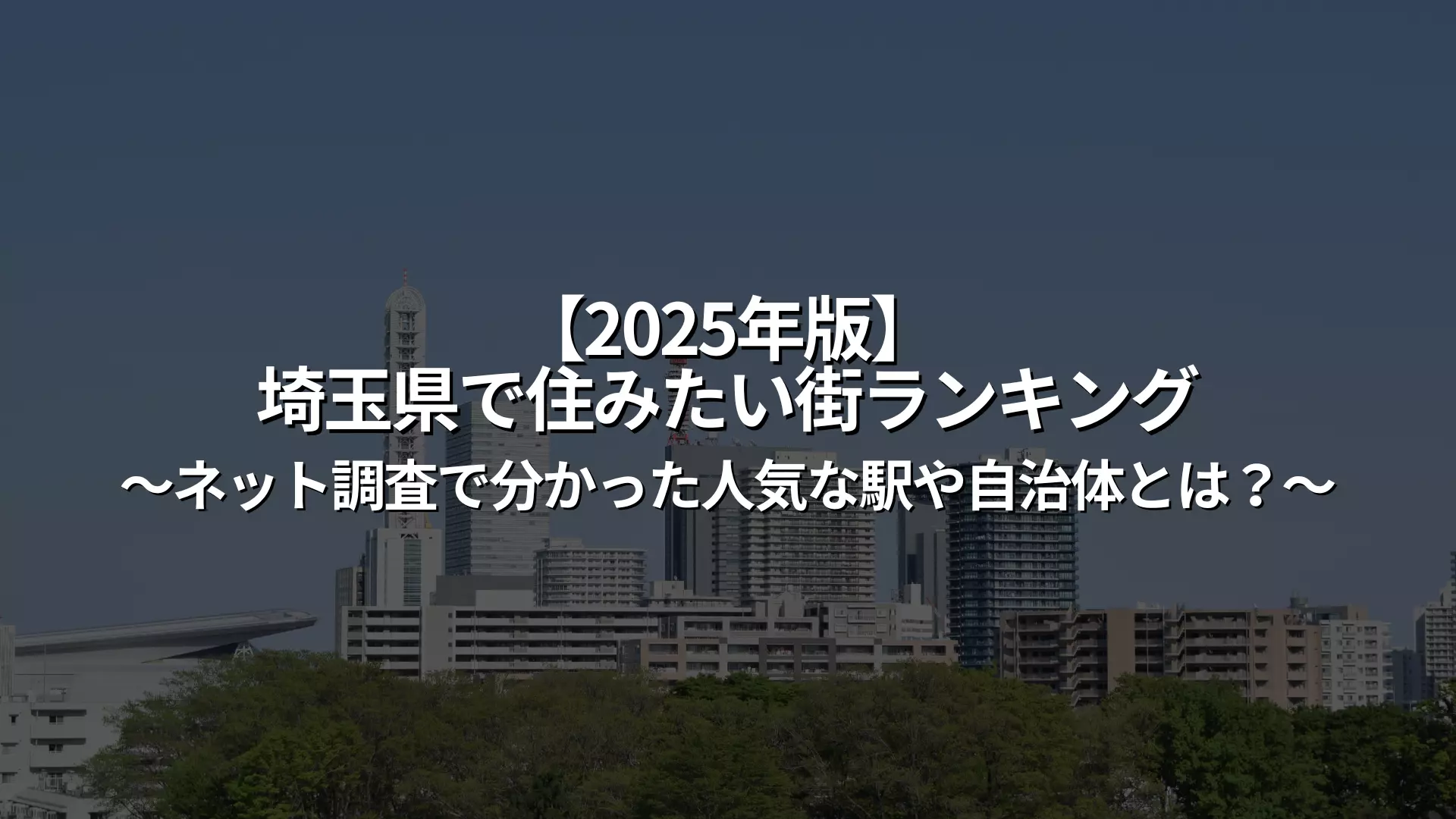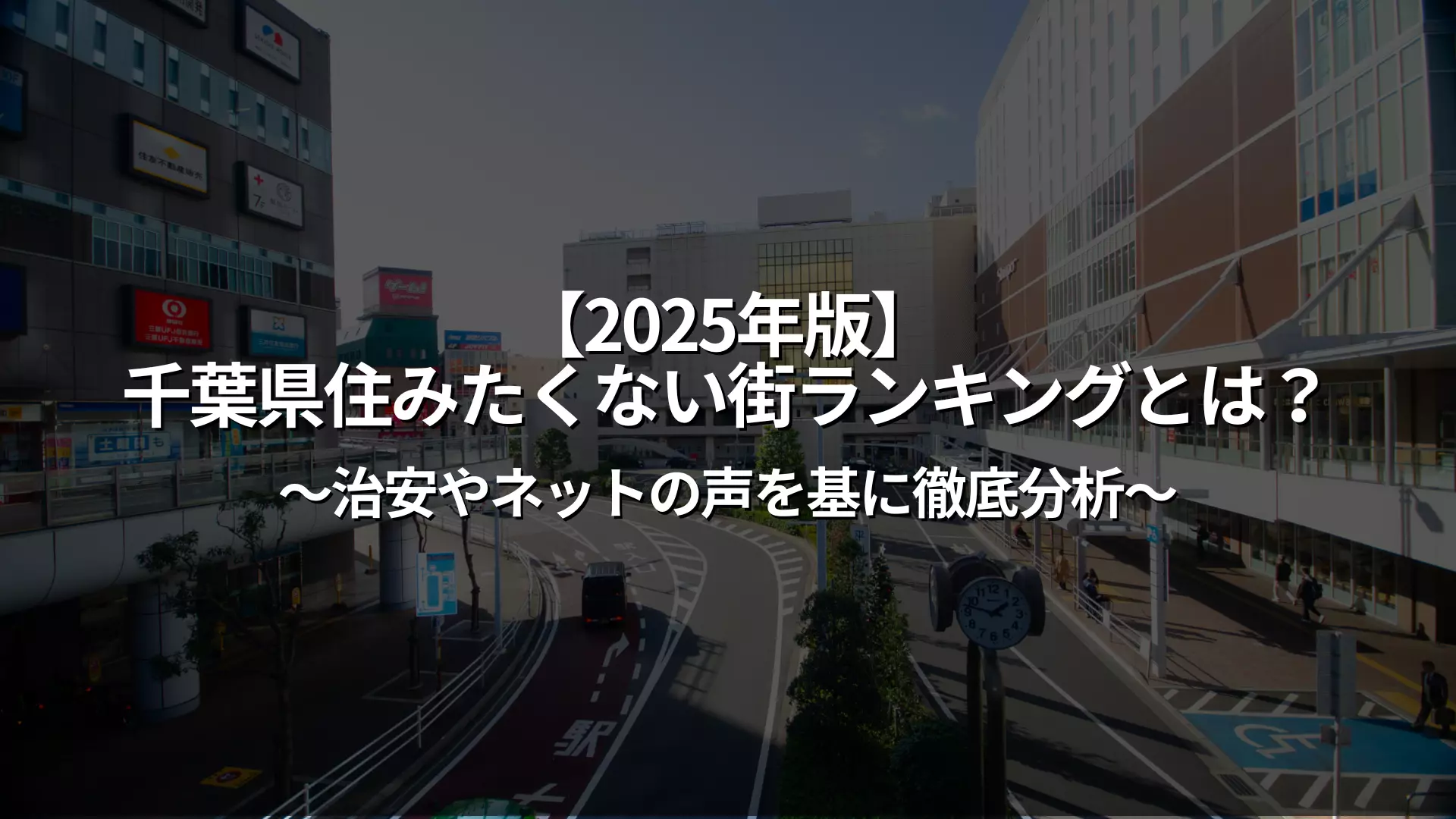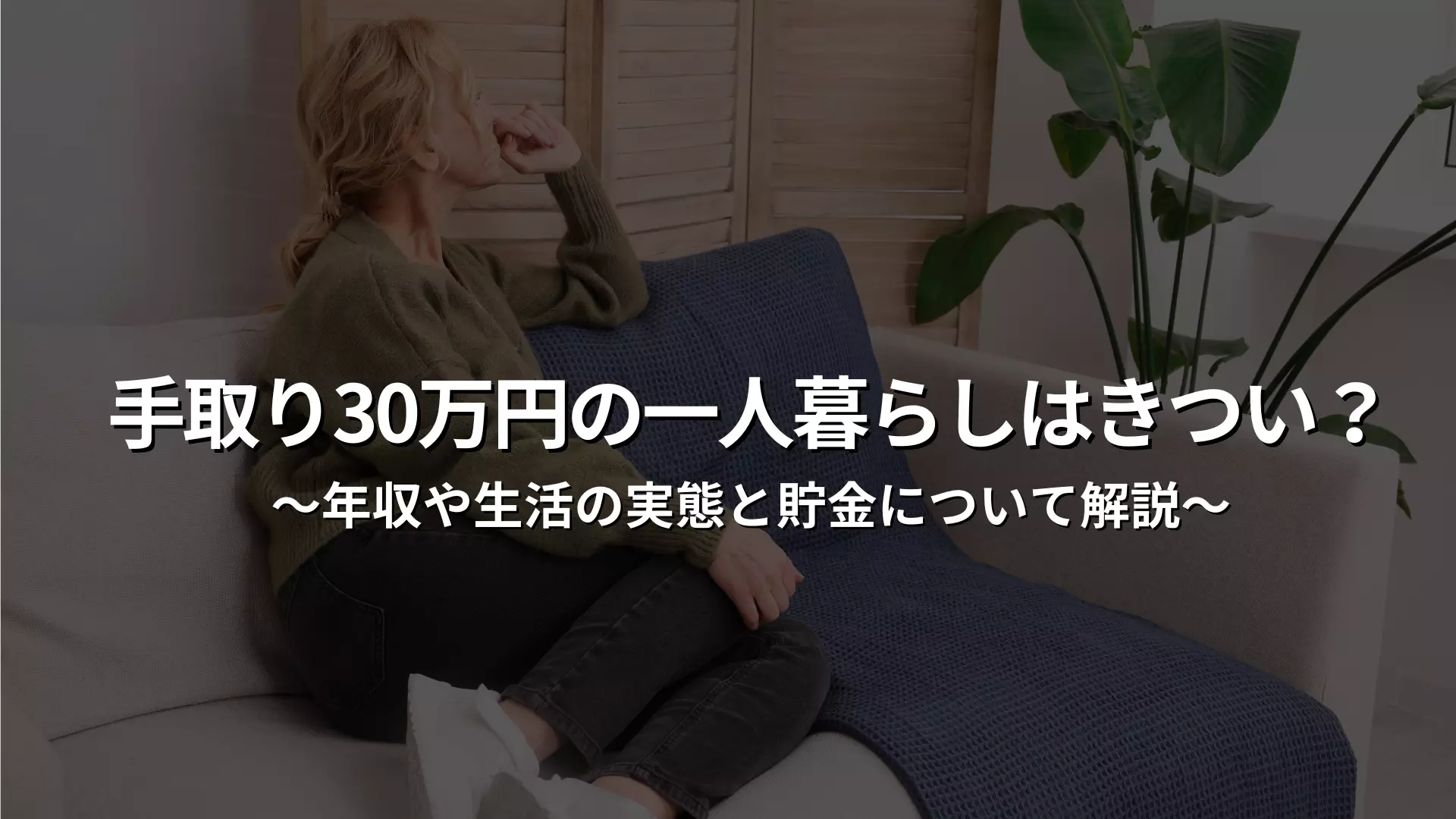日本では高齢者の単身世帯が増加し、2040年には全世帯の40%が単身世帯になると予測されています。従来の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に代わり、自由な生活を送りながら孤独を解消できる「高齢者向けシェアハウス」が新たな住まいの選択肢として注目されています。
高齢者向けシェアハウスには、多世代共生型、介護付き、外国人と共生するタイプなど多様な種類があり、ニーズに応じた選択が可能です。本記事では、高齢者向けシェアハウスの特徴やメリット・デメリット、選び方、国内外の成功事例を詳しく解説します。シニアライフの新たな選択肢として、高齢者向けシェアハウスを検討してみましょう。
高齢者向けシェアハウスとは?注目される背景
近年、高齢者向けシェアハウスが新しい住まいの選択肢として注目されています。従来、高齢者の住まいといえば老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が主流でしたが、これらに代わる選択肢として、共同生活を通じて孤独を解消し、より自由な暮らしを実現できるシェアハウスが人気を集めています。
高齢者の住まいの選択肢としてシェアハウスが注目される理由
高齢者向けシェアハウスが注目される背景には、以下のような要因があります。
1.孤独の解消
シングル高齢者の増加に伴い、「一人暮らしの孤独感」を感じる人が増えています。シェアハウスでは他の入居者と交流ができ、安心感のある生活を送ることができます。
2.生活費の節約
シェアハウスでは家賃や光熱費を分担できるため、一般的な一人暮らしよりも費用を抑えられるメリットがあります。
3.柔軟なライフスタイル
老人ホームや介護施設ではなく、自由な生活を維持しながらサポートを受けられる環境が求められています。シェアハウスでは、個室でのプライバシーを確保しつつ、共用スペースでの交流を楽しむことが可能です。
4.介護の前段階としての住まい
まだ介護が不要な元気な高齢者にとって、完全に施設へ入る前の選択肢としてシェアハウスが適しているという考え方が広まっています。
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違い
高齢者向けの住まいには、高齢者向けシェアハウス、老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った住まいを選ぶことが大切です。
まず、高齢者向けシェアハウスは、高齢者同士や多世代で共同生活を送る形態の住まいです。自由度が高く、介護サービスは基本的に提供されませんが、入居者同士の助け合いや、訪問介護を利用することでサポートを受けることができます。特に、一人暮らしの孤独感を解消し、生活費を抑えながら安心して暮らせる点が魅力です。
一方、老人ホームは、介護スタッフが常駐し、食事や入浴などの生活サポートが提供される施設です。要介護度が高い人向けで、日常生活のサポートを受けながら安心して暮らせる環境が整っています。ただし、自由度が低く、生活のルールやスケジュールが決まっている点がデメリットとして挙げられます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、基本的に自立した高齢者向けの住まいで、見守りや生活相談などのサービスが受けられます。介護サービスは基本的に提供されませんが、外部の介護サービスを利用することで、介護が必要になっても住み続けることが可能です。高齢者向けシェアハウスと比べてプライバシーが確保されやすいですが、入居費用が高くなる傾向があります。
また、グループホームは、認知症の高齢者向けの小規模な共同生活施設です。介護スタッフが常駐し、認知症の症状に対応した生活サポートが提供されます。自由度は低くなりますが、手厚い介護が受けられる環境が整っています。
このように、高齢者向けシェアハウスは、自由度の高さとコストの低さが魅力であり、自立した生活を維持しながら、他者との交流を楽しみたい人に向いている選択肢です。介護が必要になる前の段階での住まいとして、近年注目を集めています。
シングル高齢者の増加と社会的な背景
日本では一人暮らしの高齢者が増加しており、2040年には全世帯の40%が単身世帯になると予測されています。特に、配偶者に先立たれた人や、結婚しなかった高齢者にとって、新たな住まいの選択肢が求められています。
また、空き家の増加も背景にあり、自治体や不動産会社が高齢者向けシェアハウスとしてリノベーションする動きが加速しています。
「高齢者×シェアハウス」の今後の市場動向
高齢者向けシェアハウスの市場は、今後さらに拡大すると予測されています。その理由として、以下の3点が挙げられます。
1.自治体や企業の参入が増加
高齢者の居住支援の一環として、地方自治体や不動産会社が積極的にシェアハウスを展開しており、選択肢が増えています。
2.多世代共生型のシェアハウスが増加
若者と高齢者が共に暮らすシェアハウスが増え、世代間交流を促す新しい住まい方が広まっています。
3.海外の成功事例の導入
フランスやドイツでは、高齢者向けのコ・ハウジングが成功しており、日本でもそのモデルが参考にされています。
高齢者向けシェアハウスの特徴と種類
高齢者向けシェアハウスは、高齢者が共同生活を送りながら、安心して暮らせる住まいの一形態です。一般的なシェアハウスと同様に、共用スペースを活用しながら個室でプライバシーを確保できる点が特徴です。本章では、高齢者向けシェアハウスの基本的な仕組みや、一人暮らしとの違い、主な種類について詳しく解説します。
高齢者向けシェアハウスとは?
高齢者向けシェアハウスとは、高齢者が共同生活を送りながら、安心して暮らせる住まいの一形態です。一般的なシェアハウスと同様に、キッチンやリビングなどの共用スペースを利用しながら、個室でプライバシーを確保できる仕組みになっています。
高齢者向けシェアハウスが注目される理由のひとつに、高齢者の単身世帯が増加していることが挙げられます。総務省の調査によると、日本では65歳以上の単身世帯の割合が年々増加しており、2040年には全世帯の約40%が単身世帯になると予測されています。一人暮らしの高齢者は孤独感や健康リスクを抱えやすく、こうした課題を解決するために、シェアハウスが選択肢として注目されているのです。
<高齢者向けシェアハウスの特徴>
- 一人暮らしの孤独を解消できる:共同生活のため、他の入居者と日常的に交流ができ、孤独感を軽減できる。
- 生活費の節約が可能:家賃や光熱費をシェアできるため、一人暮らしよりも経済的負担を軽減できる。
- 自由な暮らしができる:老人ホームのような厳格なルールがなく、比較的自由な生活が送れる。
- 必要に応じて介護サポートが受けられる:介護付きのシェアハウスでは、訪問介護や生活支援サービスを利用できる。
高齢者向けシェアハウスの主な種類
高齢者向けシェアハウスには、入居者の生活スタイルやサポートの有無によって異なる種類があります。以下に代表的な4種類を紹介します。
①一般的なシェアハウス型
自立した高齢者が共同生活を送るシェアハウスで、特に介護が必要ない高齢者向けの物件が多いのが特徴です。住人同士で助け合いながら生活するスタイルで、共同の食事やレクリエーションを楽しめることが魅力です。
<特徴>
- 高齢者同士の交流が活発で、孤独を感じにくい
- 家賃や光熱費を分担できるため、生活費を抑えられる
- 訪問介護やデイサービスを個別に利用可能
- 費用相場:月額5万円~15万円程度
②多世代共生型(若者×高齢者)
若者と高齢者が共に暮らすシェアハウスで、世代を超えた交流を目的としています。特に、大学生や若い社会人が住み込みで生活支援を行うスタイルも増えています。ヨーロッパではすでに多くの成功事例があり、日本国内でも導入が進んでいます。
<メリット>
- 若者と高齢者が交流することで、双方に良い影響を与える
- 高齢者は若い世代との交流を通じて、精神的な活力を得られる
- 若者にとっては低家賃で生活できるメリットがある
- 成功事例として、フランスやドイツの「世代間シェアハウス」がある
③介護付きシェアハウス
介護サービスが提供されるシェアハウスで、要介護の高齢者向けに設計されている住まいです。一般的な老人ホームと異なり、より自由な暮らしを維持しながら介護サポートを受けられる点が特徴です。
<主な特徴>
- 介護スタッフが常駐、または定期訪問
- 医療機関と提携しており、介護が必要になっても住み続けられる
- 訪問介護やデイサービスを利用できるため、施設ほどの制約がない
- 費用相場:月額10万円~30万円程度
④外国人と共生するシェアハウス
国際交流を目的としたシェアハウスで、外国人居住者と共に暮らすスタイルです。特に、外国人留学生や移住者と共同生活を送りながら、異文化交流を楽しめるのが魅力です。
<実際の事例>
- 大阪の「西都ハウジング」では、60歳以上のシニア女性と外国人が共同生活
- アジア料理の交流会などを定期開催し、異文化を体験できる
- 海外では、スペインやカナダで同様のシェアハウスが増えている
お部屋を検索
高齢者向けシェアハウスのメリット・デメリット
高齢者向けシェアハウスは、一人暮らしの孤独を解消し、経済的な負担を軽減しながら自由な生活を送れる住まいの選択肢として注目されています。しかし、すべての高齢者に適しているわけではなく、生活スタイルやニーズに応じてメリット・デメリットを理解することが重要です。ここでは、高齢者向けシェアハウスのメリットとデメリットを詳しく解説します。
高齢者向けシェアハウスのメリット
①孤独を解消し、コミュニティの中で暮らせる
高齢者の一人暮らしは、孤独感やうつリスクの増加が懸念されます。シェアハウスでは、共用スペースでの会話や食事、レクリエーションを通じて自然な交流が生まれるため、孤独を感じにくくなります。また、緊急時に周囲の住人が気づきやすい環境も安心材料です。
②生活費を抑えられる
シェアハウスでは、家賃や光熱費、食費を入居者同士でシェアできるため、一人暮らしよりも経済的負担を抑えられます。特に年金生活者や限られた収入で生活する高齢者にとって、コストを抑えながら安心して暮らせる点が魅力です。
③介護が必要になる前の段階で住める
高齢者向けシェアハウスの多くは、自立した生活ができる高齢者向けです。老人ホームに入る必要はないが、一人暮らしが不安な人にとって、適度な距離感で支え合える環境が整っています。また、訪問介護サービスを併用することで、必要なサポートを受けながら住み続けることも可能です。
④老人ホームよりも自由度が高い
老人ホームでは、施設のルールに従って生活する必要がありますが、シェアハウスでは自由度が高く、自分のライフスタイルを維持できる点が大きなメリットです。外出や食事の時間を自分で決められるため、これまでの生活リズムを崩さずに暮らせることが魅力です。
⑤多世代交流や異文化体験ができる
若者や外国人と共に暮らす「多世代共生型シェアハウス」や「国際交流型シェアハウス」では、世代や文化を超えた交流が可能です。特に、若い世代とのコミュニケーションは、高齢者の認知症予防にも効果的といわれています。
高齢者向けシェアハウスのデメリット
①介護スタッフが常駐していない
高齢者向けシェアハウスには、老人ホームのように24時間介護スタッフが常駐しているわけではないため、要介護度が高くなると住み続けることが難しくなる可能性があります。介護が必要になった場合に、訪問介護やデイサービスを利用できるかどうか、事前に確認が必要です。
②入居者同士のトラブルの可能性
シェアハウスは共同生活のため、生活習慣や価値観の違いによるトラブルが発生することもあります。特に、掃除や食事のルール、騒音問題などが起こりやすいため、入居前にルールや相性を確認することが重要です。
③プライバシーの確保が難しい場合がある
シェアハウスでは個室が用意されているものの、キッチンやリビング、浴室などの共用スペースを他の住人と使うため、一人の時間を確保しにくい場合があります。自分にとって快適な距離感で暮らせるかどうかを事前に検討することが必要です。
④物件の数がまだ少ない
高齢者向けシェアハウスは増えているものの、一般的な賃貸物件や老人ホームと比べると、まだ選択肢が限られているのが現状です。特に、地方では物件数が少なく、選べる範囲が狭いため、事前に十分なリサーチが必要になります。
⑤バリアフリー設備が不十分な場合がある
一般的な高齢者施設と異なり、シェアハウスの多くは一般住宅を改装して運営されているため、バリアフリー対応が十分でない場合もあります。特に、階段や浴室の段差、手すりの有無などを事前に確認することが重要です。
高齢者向けシェアハウスの選び方
高齢者向けシェアハウスは、一人暮らしの不安を解消しながら、自由な生活を維持できる新しい住まいの選択肢として注目されています。しかし、物件によって設備やサポート体制、入居条件が異なるため、慎重に選ぶことが重要です。
本章では、高齢者向けシェアハウスを選ぶ際にチェックすべきポイントや失敗しないためのコツを詳しく解説します。自分に合ったシェアハウスを見つけるための参考にしてください。

①物件の立地・周辺環境をチェック
高齢者向けシェアハウスを選ぶ際に、まず重要なのが立地や周辺環境です。日常生活に便利な施設が近くにあるかを確認しましょう。
<チェックポイント>
- 病院やクリニックが近くにあるか(急な体調不良時に安心)
- スーパーやコンビニが徒歩圏内にあるか(日々の買い物に便利)
- 交通アクセスの良さ(バスや電車を利用しやすいか)
- 家族が訪れやすいか(定期的な面会のしやすさ)
高齢になると移動が負担になるため、できるだけ生活圏内で完結できる立地を選ぶことがポイントです。
②シェアハウスの設備や間取りを確認
シェアハウスの設備が高齢者向けに適しているかどうかをしっかり確認することも重要です。
<チェックポイント>
- バリアフリー設計か(階段が多い、段差がある物件は要注意)
- 手すりやエレベーターがあるか(移動のしやすさ)
- 浴室やトイレが共有か個別か(プライバシーの確保)
- 共有スペースの広さや清潔さ(快適に過ごせる環境か)
- セキュリティ対策(オートロックや防犯カメラの有無)
特にバリアフリー設計かどうかは、高齢者にとって快適に暮らすための大きなポイントです。
③契約形態と費用を比較する
シェアハウスの契約形態や費用は物件によって異なるため、入居費用と月額費用をしっかり比較しましょう。
<チェックポイント>
- 初期費用(敷金・礼金・保証金など)
- 月額家賃+共益費+光熱費の合計
- 食事提供の有無とその費用
- 退去時の条件(違約金や解約手続き)
- 途中で介護が必要になった場合の対応
特に、契約期間や退去条件を事前に確認し、トラブルを避けることが大切です。
④入居者の雰囲気やルールを把握
シェアハウスでは、入居者同士の関係性や生活ルールも重要なポイントです。入居後に「思っていた環境と違った」と後悔しないためにも、事前に確認しましょう。
<チェックポイント>
- 入居者の平均年齢や生活スタイル
- 共同生活のルール(食事・掃除・来客・門限など)
- 他の入居者との相性
- 管理人や運営者がいるか
- トラブル発生時の対応方法
可能であれば、事前に体験入居をして雰囲気を確認するのがおすすめです。
⑤介護・医療サポートの有無
シェアハウスの多くは基本的に自立した高齢者向けですが、物件によっては介護や医療サポートを受けられる場合もあります。将来的なことを考えて、サポート体制を確認しておきましょう。
<チェックポイント>
- 介護スタッフが常駐しているか
- 提携している医療機関があるか
- 訪問介護・デイサービスを利用できるか
- 体調が悪化した場合の対応(退去の条件など)
将来的に要介護度が上がっても住み続けられるかどうかを確認しておくと安心です。
⑥体験入居を活用する
実際に住む前に、体験入居をして雰囲気を確かめることも大切です。短期間でも住んでみることで、自分に合っているかどうか判断しやすくなります。
<体験入居で確認すべきこと>
- 入居者との相性
- 食事の内容や提供方法
- 共有スペースの使いやすさ
- 日常生活の快適さ
体験入居を実施しているシェアハウスは限られていますが、できるだけ事前に訪問し、生活環境を確認することをおすすめします。
お部屋を検索
高齢者向けシェアハウスの成功事例【国内&海外】
高齢者向けシェアハウスは、日本国内だけでなく海外でも新しい住まいの形として注目されています。特に、シングル高齢者の増加や介護費用の負担軽減、世代間交流の促進といった社会的なニーズを満たすモデルとして、さまざまな成功事例が生まれています。
ここでは、日本国内と海外で実際に成功している高齢者向けシェアハウスの事例を紹介し、どのような工夫がされているのかを解説します。
国内の成功事例
①若者と高齢者が共に暮らす「多世代共生型シェアハウス」(東京都)
東京都内では、高齢者と若者が同じ空間で生活する「多世代共生型シェアハウス」が増えています。あるシェアハウスでは、大学生や社会人が低家賃で入居し、その代わりに高齢者の生活サポートを行う仕組みを導入しています。
<成功のポイント>
- 高齢者は若者と日常的に交流することで、孤独感の軽減や認知症予防につながる
- 若者は低コストで住めるうえ、高齢者との交流を通じて社会経験を積める
- 運営会社が入居者同士の関係をサポートし、トラブルを未然に防ぐ工夫をしている
このシェアハウスでは、入居者同士の交流を促すために食事会や趣味のワークショップを定期開催しており、入居者の満足度も高いのが特徴です。
②介護サービス付きシェアハウス「ケア付き共同生活」(大阪府)
大阪府では、介護が必要な高齢者向けのシェアハウスが増えています。特に、介護スタッフが常駐し、必要なサポートを受けながら生活できるシェアハウスが注目を集めています。
<成功のポイント>
- 入居者の健康状態に応じて、訪問介護やデイサービスを柔軟に利用できる
- 医療機関と提携し、緊急時の対応がスムーズ
- 従来の老人ホームより自由度が高く、個人のライフスタイルを維持できる
このシェアハウスは、要介護1~2程度の高齢者が住みやすい環境を提供し、入居者からも「老人ホームより気軽に入居できる」「費用が抑えられて助かる」と好評です。
③シニア女性と外国人が共生するシェアハウス(大阪府)
大阪では、高齢者と外国人が共同生活を送るシェアハウスが登場し、異文化交流を楽しみながら暮らす新しい住まいの形として人気を集めています。
<成功のポイント>
- 高齢者にとっては異文化に触れることで刺激になり、生活の楽しみが増える
- 外国人にとっては、日本文化を学びながら低家賃で住める
- 定期的な交流イベント(料理教室・語学学習など)を開催し、関係構築をサポート
このシェアハウスでは、特にアジアからの留学生が多く、高齢者と一緒に料理を作ったり、日本の文化を教え合ったりすることで自然な交流が生まれているのが特徴です。
海外の成功事例
①世代間シェアハウス「ル・パリジェン」(フランス)
フランスでは、高齢者と若者が共に暮らす「世代間シェアハウス」が成功事例として注目されています。「ル・パリジェン」は、大学生が高齢者とルームシェアすることで、家賃を低く抑えながら助け合いの精神を育むことを目的としています。
<成功のポイント>
- 高齢者は若者と交流することで、孤独感の軽減や健康維持につながる
- 大学生は、安価な家賃でパリ市内に住める
- 週に数回、食事を一緒にしたり、簡単な家事を手伝うことで相互サポートが生まれる
この取り組みは、ヨーロッパ各地で成功モデルとして広がりつつあり、日本の「多世代共生型シェアハウス」の先駆けともいえる事例です。
②高齢者専用コハウジング「シニアヴィレッジ」(ドイツ)
ドイツでは、高齢者専用のコハウジング「シニアヴィレッジ」が注目されています。これは、完全に高齢者だけで生活するシェアハウス型の住まいで、入居者同士が助け合いながら暮らすコミュニティ型の住宅です。
<成功のポイント>
- 入居者が「住人組合」を作り、生活ルールを自主的に決める
- 介護が必要になった際は、訪問介護や医療サービスを活用できる
- 個人のプライバシーを確保しながら、共同生活のメリットも享受できる
「シニアヴィレッジ」は、従来の老人ホームに比べて自由度が高く、自立した生活を送りたい高齢者に最適な選択肢となっています。
まとめ
高齢者向けシェアハウスは、自由な生活を維持しながら孤独を解消し、経済的負担を軽減できる新しい住まいの選択肢として注目されています。一般的なシェアハウスのほか、多世代共生型や介護付き、外国人との共生型など多様な形態があり、ニーズに応じた選択が可能です。
また、国内外の成功事例からも、世代間交流や地域とのつながりを活かした住まいが高齢者にとって有益であることが分かります。今後、自治体や企業の参入が増え、さらに選択肢が広がると予想されるため、自分のライフスタイルに合った最適な住まいを見つけることが重要です。
物件検索はこちら